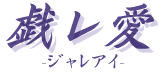
るろうに剣心
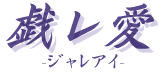
- 新章 -
作・みゃあ
▼ ▲
剣心が入ってきた。
薫は「あ」、と声を漏らして、瞬間、肩をすぼませた。
剣心を感じた。
先程は、痛みと衝撃に気付く間もなかったが、今度は、彼の体温と存在をはっきりと膣内で感じる。
力強く、熱い…。
彼を受け入れているのだという想いが、薫の心を震わせる。
それは、一層の疼きとなって、胎内を締め付けた。
「……!」
その収縮に反応したように、剣心の細身の身体がぴくりと慄えた。
そして、堪えきれなくなったのか、僅かに前進する。
「ん…っ」
破瓜の傷はまた新しく、沁みるような痛覚が薫の尻を一歩、退かせる。
無意識の裡に、内股が後込みして、剣心の腰を押し返していた。
「薫殿……」
「……っん、ごめん。…平気」
「………」
短いやり取りで、二人は互いの想いを伝えた。
それでもなお、剣心はすぐには腰を進める気になれず、薫の頬に手をやる。
火照った肌の質感に、涙の通り道だけが、ひんやりとした感触を残した。
ふと、薫の髪に目をやる。
敷布の上に、夜目にも艶やかな黒髪が、華のように広がって、複雑な紋様を描き出している。
「………」
「……剣心?」
あまりにもじっと見詰められて、薫は眉を寄せた。
「……解くと、ヘン…?」
漆黒の瞳の中に、愛しい人の姿を映したまま、剣心はゆっくりと頭(かぶり)を振った。
薫の愛らしさは少しも変わることなく、可憐さと同時に、年相応の色気を匂わせている。
剣心は、無言で放射状に広がった薫の黒髪を撫でた。
なめらかな感触が、掌に心地よい。
肌と違ってひんやりとした感触を愉しむように、敷布の上で黒髪を幾度も撫で付ける。
神経など通っているはずもないのに、薫は慄えるような快感に身を捩った。
どうも、意識している以上に、自分は薫が愛おしくて仕方ないらしい。
改めて、そのことに気付いた。
気を抜くと、細腰を抱く腕に、必要以上に力が入ってしまいそうになる。
側にきてほしいのだ。
身内に湧き起こる衝動に耐えきれずに、剣心はぐっと腰を沈めた。
薫の襞(ひだ)を割り入る。
粘液が己の分身に絡みつき、えもいわれぬ快楽が、脳髄を痺れさせた。
薫は声もなくのけぞった。
一つになりたいとの欲求は、独占したいという欲望の現れだ。
無意識に発した、その強烈なまでの剣心の意志を直(じか)に子宮に受け、薫は啼(な)いた。
歓びに、啼いた。
受け入れたい。
痛切に、そう思った。
心が、躰が、剣心を求めている。
どうしようもない。
なぜ、こんなにも愛おしいのか。
寂寥にも似た情が、いくら注いでも満たされぬ杯のように、求愛する薫の胸を締め付ける。
知らぬ間に、涙が零れた。
どうしたら、もっとこの人の側にいけるのか。
いっそ、本当にひとつになってしまえたら…。
そうすれば、引き裂かれる喪失感を想像せずにすむようになるのだろうか。
その間隙を埋めて欲しい。
剣心で、埋めて欲しい。
薫にできるのは、良人にしがみついて、膣で彼の昂ぶりを必死に締め付けるだけだった。
薫の胎(なか)は、あたたかく濡れて、剣心を迎えた。
躰の中心に、薫が絡みつく。
絡みつき、扱(しご)く。
扱いては、嘗(な)める。
「…ぅ…」
思わず呻いた。
自分の中に、これほどの情念の炎(ひ)が残っているとは意外だった。
情動など、忘れ去ってしまったものと思っていた。
ただ、今は薫の胎内に埋めたい。
すべてが薫を求めている…。
ふと、薫は我に返った。
自分の女の部分に、剣心の荒々しい昂ぶりを感じる。
下から、上から、衝き上げられる揺らぎに身を任せながら、良人の顔を仰ぎ見る。
愛しさが、こみ上げた。
剣心が、少年のような顔で、懸命に腰を送り込んでいる。
無心に快楽を貪る姿が、むしろ、薫の顔を綻ばせた。
求められている。
嬉しい…。
自分の躰で、剣心を悦ばせることができるのだ。
彼の顔が、抑えきれない悦楽に歪むたび、薫は満たされるのを感じる。
はっ…はっ…はっ…はっ…
…ぅ…んっ…は…ぁぁ…んん…
男と女の息遣いが、寝間を満たした。
湿った音が耳道に溢れて、頭を痺れさせる。
剣心が腰を衝き入れるたびに、薫の中心から溢れ出した蜜が、細い小径を伝い、狭い後ろの窄まりを擽(くすぐ)る。
その感触に、薫は身悶えた。
恥ずかしい程に、濡れている。
剣心が、子宮のとば口に辿り着くたびに、奥から溢れ出し、敷布まで濡らしてしまう。
薫は、紅潮した頬をさらに羞恥に染めながらも、必死で剣心に応え、さらなる注挿を求めた。
「剣心…けんしん…」
「……薫殿…?」
呼ばれて、はたと我に返る。
それほどまでに、薫の身体にのめり込んでいたのかと思うと、なんとも気恥ずかしい気がした。
年甲斐もないな、と思い、目を糸のようにして「おろろ」という顔をする。
それが、彼の恥じらい方だった。
「剣心…どこへもいっちゃ、ヤダ……ヤダ…ヤダよ…ぅ」
強く抱き竦(すく)められていたため、腕を伸ばすことができない薫は、涙目をさらに潤ませて、首を伸ばして剣心に擦り寄った。
悲しくもないのに、何故、胸が痛いのだろう。
抱き締めれば、するりと、この腕を抜けていってしまいそうな、不安感。
子犬がそうするように、剣心の喉元に、薫は頬を擦り付けた。
汗の匂いの中に、はっきりと剣心の匂いを感じる。
「薫殿…」
激しく動いたせいか、何時の間にか薫の口元に絡みついていた、濡れそぼった後れ毛を剣心は優しく除(の)けた。
つくづく甲斐性がないことだ。
根無し草のように定まらない、我の存在の希薄さが、これまで幾度、妻である人の心を寂寥に苛(さいな)ませてきたのだろう。
「ここにいるでござる」
剣心の指が、幾度も薫の頬を撫でた。
あやすようにではなく、求めるように。
強く、薫を求めることで、剣心は自らの誓いを妻に伝えた。
薫の胎内で、存在を誇示するように、誓いを刻みつけた。
「薫殿の傍(かたわら)に」
「あぁ……」
抜けるような吐息を漏らして、薫は泣き笑いを浮かべた。
それは安堵だったのか、快楽だったのか…。
剣心の腕が後ろに回され、薫の腰を引き寄せる。
より深く、二人は繋がった。
剣心の掌が、薫の小さな尻を捏ねる。
びくりと痙攣し、きゅっと筋肉が収縮した。
しっとりとした感触の柔肉が、その微妙な振動を胎内の強張りに伝える。
剣心も慄えた。
「剣心…剣心…剣心…剣心…!」
譫言のように繰り返しながら、薫は必死に縋(すが)り付いた。
熱を帯びた乳房が、剣心の胸板との間で押しつぶされ、膨らみきった先端のしこりが、気が遠くなるような愉悦を運んでくる。
秘唇の上の、薫の慎ましやかな和毛は、二人の体液で、しとどに濡れそぼっていた。
朦朧としかける意識の中、もう痛みは感じなかった。
胸を刺す寂寥感も。
「あっ…あっ…あっ、あっ、あっ…あーーーっ…!」
膣を擦られ、子宮を叩かれ、のけぞったところへ唇を奪われ、薫は一気に高みへと押し上げられた。
がくがくと崩れ落ちそうな絶頂感のさなか、ぐうっ、と腰を引き寄せられ、胎内で剣心が大きくなった。
薫…っと叫んで、剣心は弾けた。
熱い…熱い迸りが、最も深いところで爆(は)ぜて、薫は立て続けに上り詰め、気を遣った。
薫、と呼ばれ、さらに二度…。
これ以上ない深い繋がりに、薫は剣心と同じ愉悦を共有した。
薫は幸せだった。
り……りー、りー…
「…ぁ…虫の音…」
「もう、秋が近いでござるな…」
火照りの余韻の残る剣心の胸に頬を埋めて、薫は、聴こえて来た音色に、目を細めた。
彼女の良人は、常と変わらぬ口調で応じる。
その声色に、穏やかさが増したのを敏感に感じ取って、薫は頭を浮かせて、剣心の顔を覗き込んだ。
穏やか…というよりも、少し間の抜けたような、まるい微笑み。
「…?どうか、したでござるか」
「…なんでもないでござるよ、剣心」
「おろ?」
出会った頃の、その表情を思い出して、薫は顔中をくしゃくしゃにして満面の笑みを浮かべた。
あの頃に戻ったわけではない。
数々の癒えぬ痛みを経て、ようやく、心の平穏が戻ったのだ。
かつての傷を抉り出して、なお。
薫はそれを感じた。
だから、笑った。
野兎が、それ以上潜れぬ穴に、さらに身を潜めるかのように、薫は剣心の腕の中に身を丸め、擦り寄った。
薄衣一枚、身に纏わぬ互いの体温が、これほど心地よく感じられることはない。
「こ、こそばゆいでござる」
「………」
薫は、剣心の非難には応じず、さらに頬を擦りつけた。
「……さっきの、本当?」
「薫殿…?」
ぎゅっと胸板に顔を埋め、表情を隠したまま、薫が訊ねる。
「どこにも……いかない?」
剣心は、目をぱちくりと瞬かせ、そして、口元を綻ばせた。
「行かない」
「私の、傍にいてくれる?」
「もちろんでござる」
「私…嫉妬深いよ。剣心がほかの女の人と話してるだけで、焼き餅やくかも」
「どうぞでござる」
平然と、剣心は澄まし顔で応じた。
「一日中、剣心にべったりしがみついたりするよ」
「ど、どうぞでござる」
「寝間だけじゃなくて、縁側でも、茶の間でも…厠までついていくかも」
「う゛……そ、それはちょっと…」
「………」
「せ、せめて、湯殿くらいまでなら」
指を一本立てて、冷や汗混じりに、ひきつった口元で妥協を促す剣心に、薫はぷっと吹き出した。
「…冗談よ。…でも、一緒に入る?湯浴み」
「い、いや、今のはものの喩えでござって…」
言ってしまってから、薫は自らの言葉に想像力をかき立てられてしまい、勝手に赤面した。
もし、剣心が承諾したら、泡を食うのは自分の方だろう。
なに言ってるのかしら、私…。
視線を上げると、互いの視線がぶつかり合った。
裸身のままに身を寄せ合っていることが、急に恥ずかしくなって、さっと身を離すと、互いの夜着をそそくさと身に付け始める。
月明かりに、乾きかけた情事の痕を見つけるたびに、薫は頬どころか全身を朱に染めた。
剣心の精を注がれている間中、その脚を必死に絡みつかせていたことを思い出し、蒸気を吹き上げる。
ちら、と良人の背をのぞき見ると、自分がつけたと思われる、紅い線が幾本も走っていた。
薫は、あわてて目を逸らした。
見れば、自分の肩口にも、剣心のつけた所有印が、淡いあざとなって残っている。
頭がくらくらした。
やがて、白い揃いの夜着の前を合わせた二人は、肩越しに見つめ合って、ハハハハハ、と笑い合った。
それが照れ隠しであることは明確だった。
その夜は、気恥ずかしくて、そのまま一言も交わすことなく、床についた。
もう、身を寄せずしても、互いの温もりを感じることができた。
どちらから求めたのだろう。
……目覚めた時には、しっかりと、その手が繋がれていた。
(もう少し、つづく)
(update 01/12/10)