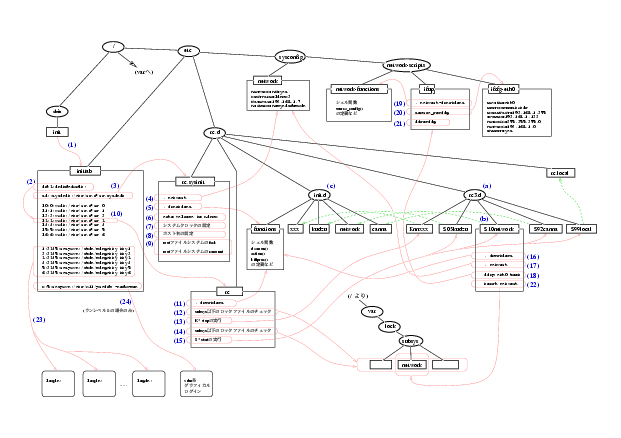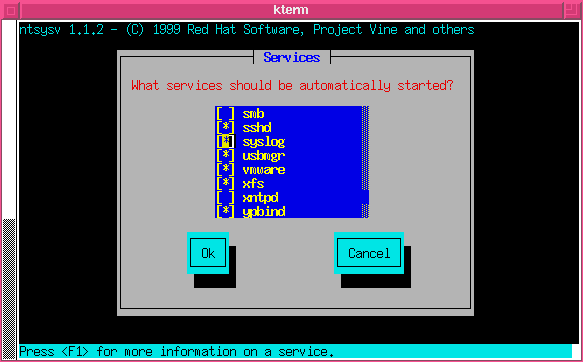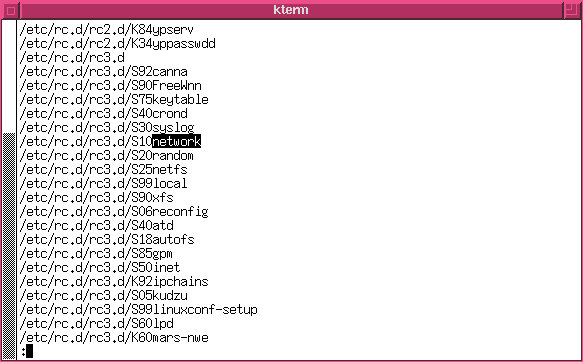/etc/rc.d/rc3.d以下には多数のSファイルがありますが,
この中から代表してS10networkの動作を見て行きましょう.
まず最初に,ほかのスクリプトと同様に,functionsとnetworkのファイルが
読み込まれます.(PDF図(16),(17))
このあとS10networkでは,最終的にはifconfigコマンドによる
ネットワークインターフェイスの立ち上げが行なわれるはずです.
しかし,実際のスクリプトでは/etc/sysconfig/network-scripts以下にある
さらに別のスクリプトを呼び出すなどの複雑ことをしているため,
S10networkを読みこなすのは少々大変です.
S10networkのうち,主要部分を抜き出して簡略化すると下のリスト(S10networkの主要部分の簡略リスト)のようになります.
ここではスクリプト内のcdコマンドにより,
/etc/sysconfig/network-scriptsにカレントディレクトリを変更していることに
注意して下さい.(リスト(1))
*リスト S10networkの主要部分の簡略リスト
cd /etc/sysconfig/network-scripts ← (1)
変数interfacesに,存在するインターフェイス名(lo0などは除く)をセットする ←(2)
case "$1" in
start)
for i in $interfaces; do ← (3)
action "Bringing up interface $i" ./ifup $i boot ← (4)
done
touch /var/lock/subsys/network ← (5)
;;
stop)
…省略…
;;
…省略…
esac
|
次にinterfacesという変数に,存在するインターフェイス名をセットします.
これは,/etc/sysconfig/network-scripts以下にある,
ifcfg-eth0のようなファイル名を見て,その末尾のeth0という文字列だけを取り出して
変数interfacesに代入するという方法で処理が行なわれます.(リスト(2))
なお,Linuxでは,ネットワークカード(以下NIC)の種類に関わらず,
イーサネットのインターフェイス名はeth0,eth1,...のように付けられます.(※注)
NICを1枚だけ使用しているマシンでは,eth0のみが変数interfacesに代入される
ことになるはずです.
-
※注
-
NICに対応した実際のドライバについては,
/etc/conf.modules(またはmodules.conf)の中に,
「alias eth0 eepro100」(Intel EtherExpressPro100の場合)のように記述して
設定します.
そしてcase文によるstart引数の場合分けあと,
各インターフェイスに対してfor文のループでネットワークが立ち上げられます.
(リスト(3))
NICが1枚だけのマシンではループは1回だけ実行され,
結局「./ifup eth0 boot」というコマンドが実行されることになります.
(リスト(4),PDF図(18))
ここではifupコマンドの頭に「action "Bringing up interface $i"」というものが
付いていますが,actionというのは/etc/rc.d/init.d/functionsの中で定義されている
シェル関数であり,これはおもにコンソールに緑色の[ OK ]というメッセージを
表示するために使用されています.
(コラム「シェル関数action()を直接使ってみよう」参照)