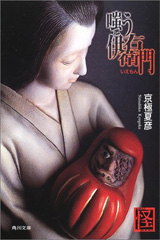◆ 歯皮膚屁本 - はひふへほん ◆ HOME
<前 | 日付順目次 | 書名索引 | 著者名索引 | 偏愛選書 | 次>
読書日記 2002/07-12
- 嗤う伊右衛門 京極夏彦
- マーティン・ドレスラーの夢 スティーブン・ミルハウザー
- コカイン・ナイト J・G・バラード
- 逃げ水半次無用帖 久世光彦
- カブキの日 小林恭二
- 理由 宮部みゆき
- ドラキュラ戦記 キム・ニューマン
- 虚構市立不条理中学校 清水義範
- 鏡の中は日曜日 殊能将之
- 貴族の階段 武田泰淳
次点が同率二冊
赤い百合 アナトール・フランス
イリーガル・エイリアン ロバート・J・ソウヤー
あくまで、私が今年読んだ本が対象、一作家一冊限定。
今年はすべて小説になってしまった。「感動した」が基準なので、どうしても小説有利だけど、来年はランクインさせられるような目からウロコのノンフィクションもたくさん読みたいものだ。
今年の読了本は65冊。読了記の更新が大幅に遅れてていて空白だらけだけど、可及的すみやかに埋めていきます。とりあえずタイトルだけはすべて並べて自分にプレッシャーをかけてみたのだけど・・・・
香山滋といえばゴジラの生みの親、もちろん松井の父ではなく『怪獣ゴジラ』の原作者だ。本書以外では短編をいくつかしか読んでいないが、SFというより幻想小説または変格探偵小説の色濃い作品が得意のようだ。
本書には『魔婦の足跡』と『ペット・ショップ・R』の二つの中編が収録されている。どちらも昭和30年代らしい荒唐無稽さとロマンチシズムの横溢した、今では読めない類いの妙な味わいがあるミステリーだ。ストーリーや文章は同時代に活躍した横溝や風太郎におよぶべくもない。プロットはいい加減、科白も大時代だ。しかし、キャラのたった登場人物と色彩豊かな雰囲気は、はまるとなかなか捨てがたいものがある。
表題作の方は、主人公の童話作家のところに突然「謎の美少女」が現われるのが発端だ。誘惑のような恫喝のような思わせぶりな会話で主人公を翻弄して消えるが、彼女は作家の恋人や知人のところにも現われ脅迫まがいの言辞を弄していた。実は脅迫された三人にはそれぞれ裏の顔があり、少女はその秘密をつかんでいるらしい。前半は三人と少女のかけひきを主体とした都会派サスペンスだが、後半になると三人は突然孤島に逃避してしまい少女も彼らを追いかけてきて、エキゾチックな秘境冒険小説になってしまう。
クライマックスには凶暴な人喰い昆虫が発生したり、主人公の恋人の職業が珍しい生物の剥製標本造りだったり、作家の雇い人がサソリを飼っていたり、続々登場するグロティスク生物がゴジラの作者らしい。
『ペット・ショップ・R』の方はなんとレズビアン小説である。
新聞記者の恋人を持つ美貌の主人公が、ペットショップの美人経営者に法外なギャラで引き抜かれるのだが、この大金持ちの経営者がレスボスなのだ。そのペットショップが山椒魚や肺魚などのグロティスク系ばかりを扱っているのがいかにも香山滋だが、怪魚たちはもっぱら雰囲気造りの役目のようであまり小説のストーリーにはかかわらない。それでもラストで乾上がった水槽の底に繭を作って眠る肺魚のイメージはなんとも美しい。他の登場人物には女経営者のパトロンの紳士。女経営者の前の恋人だった女性。生死もわからぬ現在の夫。ペットショップの雇い人の老夫婦。それぞれ謎をかかえている。彼らの暗闘や主人公がレズビアンに目覚めるところなど、なかなかダイナミックな心理劇で私には表題作より面白かった。そのぶん登場人物たちの科白も性格も大仰で、いささか鼻につくのは否めないが。
作者の美女への憧憬が感じられるレズビアン描写は、なかなかにエロティックで美しい。
どちらの作品も、いわゆる「貞淑な女」とか「可憐な少女」とかが出てこない。出てくる女性、みな美女だが、すべて一筋縄でいかぬしたたかさとぎらりとした欲望の持ち主たちで、そこがモダンできりりとかっこいい。
『銀河パトロール隊』『グレーレンズマン』に続くレンズマン・シリーズの第三作。前作の感想に付け加えることもあまりない。痛快スペースオプラの古典、物語もいよいよ佳境である。
今回、主人公のレンズマンは悪の独裁者に支配されていた惑星を「開放」し、銀河連邦にふさわしい文明にすべく指導していくのであるが、その方法が、なんだか敗戦後の日本を訓導したGHQのやり方にそっくりで苦笑してしまった。「イラクを占領したら日本方式で統治する」と米首脳筋が語ったらしいけど、ありうるなあ。
 ところで、本書の表紙はいわずとしれた生頼範義画伯だ。決して悪くはないし、私は好きだが、本書の中身はこれほど濃くはない。
ところで、本書の表紙はいわずとしれた生頼範義画伯だ。決して悪くはないし、私は好きだが、本書の中身はこれほど濃くはない。
三十年も昔の前の版では表紙も挿画も真鍋博画伯だった。今回とはまったく対象的な画風だった。私のレンズマンの以前読んだ記憶はかなり、この挿し絵の印象に左右されている。本書の解説で金子隆一氏もこう書いている。
最初にあの文庫本のカバーを目にしたときには、もうちょっとクールな内容を期待していたことは確かだが、今にして思えば、あの真鍋博画伯のワン・アンド・オンリーの画風によるイラストはあまりにも洗練過ぎていて、読者の目をスミス的世界の本質からだいぶんずれた方向へ導いてしまっていたのかもしれない。
まったく同感であります。しかし真鍋博の挿し絵も懐かしいのだよなあ。
 著者はコロンビア大で博士号をとった気鋭の生命科学者だったが、30年ほど前に原因不明の病に襲われ、研究所を解雇されてしまう。一時は自分の意思で食べ物を取れなくなり点滴による栄養補給での生活になり医師に安楽死を要求するほどになったが、老年に至り奇跡的な回復をとげ、その様子はNHKでも放送された。
著者はコロンビア大で博士号をとった気鋭の生命科学者だったが、30年ほど前に原因不明の病に襲われ、研究所を解雇されてしまう。一時は自分の意思で食べ物を取れなくなり点滴による栄養補給での生活になり医師に安楽死を要求するほどになったが、老年に至り奇跡的な回復をとげ、その様子はNHKでも放送された。
闘病生活中も生命科学者としての思索を続け、単なる生物学以上の生死の意味や精神の進化にまで踏み込んだすぐれた著作をたくさん書かれている。本書もその一冊。
「生命の歴史」「人類の誕生」「脳の進化」という生命科学のテーマを平易に説明してくれている。それを男女の恋物語の形式で語っているのがユニークだ。カップルはクラシックコンサートで出会った女性ピアニストと青年生命科学者。ちょっと気どった設定だが、端正な著者の語り口にはよく似合う。二人が重ねるデートの中で、女性の卒業論文のために男性が生命科学の講義をするという趣向だ。
やはり、生物学をややはなれ、意識や生死の概念を生命科学で語るあたりが面白い。ユングの「集合的無意識」をDNAに秘められている36億年の生命の歴史から説明したり、脳内快楽物質を「生物の死への適応」とみたり、魅力的な考察がたくさん出てくる。
闘病体験からくるものか、生命世界から精神世界に至る著者の思考は、宗教的な色彩さえ帯びてくるが、決して「神」を結論とせず、科学的思考の過程にあらわれた「悟り」であるのが、好ましい。
 「禁演落語」と言ってもお上に禁じられた落語ではない。戦時中時局にふさわしくないだろうと、業界=落語家がみずからが自粛した落語を指す。浅草本性寺に「はなし塚」を建て53の演題を葬ったというのだからご丁寧なことだ。「お上の意向を阿吽の呼吸でうかがい」「長いものに巻かれる」日本人の面目躍如たるものがある
「禁演落語」と言ってもお上に禁じられた落語ではない。戦時中時局にふさわしくないだろうと、業界=落語家がみずからが自粛した落語を指す。浅草本性寺に「はなし塚」を建て53の演題を葬ったというのだからご丁寧なことだ。「お上の意向を阿吽の呼吸でうかがい」「長いものに巻かれる」日本人の面目躍如たるものがある
だから演目はいわゆる「艶笑落語」とは限らない。国家総動員が公布されてるのに遊んでる場合かということで、女郎買いもの、大酒飲みものは自粛。故国に妻を残して出兵している兵隊のことを考え、間男もの、姦通ものは自粛。なんとも心やさしいことである。
敗戦後は当然解禁されたわけだが、今度は占領軍の意向によって上演できないものが出てきた。といってもあからさまな「命令」があったわけではない。「GHQ勧告」にしたがってまたもや「自粛」したのである。今度は少し傾向が違って、仇討ちものや人種差別的な内容、婦人の服従を賞揚したものなどが対象になった。
今はこうして全てが活字で読むこともできるわけだが、実際に高座で聞けるとは限らない。演者そのものがいなくなってしまった噺も多い。その意味で貴重な内容なのだが、噺によっては抜粋だけのものもあり、いささか内容的には物足りない。収録された落語そのものより、「はなし塚」の顛末の方が面白かった、というしまらない下げでおしまい。
伊右衛門は包みこむように、そっと抱いた。
「岩。もう良い。儂が――心得違いをしておった」
「旦那様」
その時。
ぞろり、と何かが動いた。
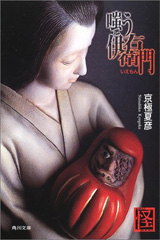 伊右衛門とは、もちろん『東海道四谷怪談』の色悪役民谷伊右衛門。この歌舞伎でも映画でもお馴染みの物語を題材にして、京極夏彦は独自のモダンな怪談――京極ワールドを繰り広げる。
伊右衛門とは、もちろん『東海道四谷怪談』の色悪役民谷伊右衛門。この歌舞伎でも映画でもお馴染みの物語を題材にして、京極夏彦は独自のモダンな怪談――京極ワールドを繰り広げる。
本書はホラーとして十二分に恐ろしい。しかし、全編を不吉で妖異な雰囲気が覆っていながら、真の意味での怪異は起らない。意外な犯人や意外な動機というミステリ要素もたっぷりある。このへんは「京極堂」シリーズにも通じるところだ。
そして、登場人物の善悪が従来の『四谷怪談』の設定から、がらりとひっくり返されている。伊右衛門は底の読めない男だが、悪人ではない。お岩は忍従の妻ではなく、近代的な自我を持つ凛とした侍の娘である。按摩の宅悦も直助権兵衛も、根っからの悪人ではなくちょっと侠気もある小悪党に描かれている。希代の悪役を振られるのは意外な人物だ。
なにより、お岩の面相が登場する時点、伊右衛門と結婚する前から崩れているという設定がすごい。そこから婚礼まで持っていく筆力はまさに力業だ。本書はお岩伊右衛門のせつないラブストーリーなのである。そして悲しいかな、デスコミュニケーションの物語だ。お岩伊右衛門だけでなく、登場する人々は互いに喜怒哀楽憎悪愛情軽蔑憧憬、あらゆる感情をたぎらせながら対手には真っ直ぐに伝わらない、伝えられない。そこからシェイクスピア的悲劇がいやおうもなく展開していく。
魅力的な登場人物の造型、端正な科白の妙、『魍魎の筺』を思わせる妖美なラスト。私の読んだ京極夏彦本では、文句なく最高傑作です。
◇
映画や歌舞伎のTV中継でしか知らないのがもどかしくなり原典を買おうかと考えていた。ところが昨日父親の家に行ったら、あるではないですか。鶴屋南北『東海道四谷怪談』(新潮日本古典集成)。早速借りてくる。正月休みはこいつを読むとしよう。
 著者は私より少し年上だが、まあ70年安保にかすった同世代(私のときは終わっていたが)。今は漫画評論家、BSマンガ夜話のコメンテータとして活躍中。自分の鬱屈した青春時代を、マンガの勃興期の作品と重ねて描いている。
著者は私より少し年上だが、まあ70年安保にかすった同世代(私のときは終わっていたが)。今は漫画評論家、BSマンガ夜話のコメンテータとして活躍中。自分の鬱屈した青春時代を、マンガの勃興期の作品と重ねて描いている。
登場するマンガが、同世代には懐かしいこと。白土三平、石森章太郎、水木しげるといった有名どころもでてくるが、大半は佐々木マキ、永島慎二、鴨川つばめ、バロン吉元といったマニアックなチョイスだ。
え?知ってる?・・・・なら、これではどうだろう。岡田史子、宮谷一彦、深井国、園田光慶。
いずれも一時代を画したり、当時、「マンガの未来を担う」と期待されていた面々だ。本当に彼らの作品には、新しいマンガへ進化する遺伝子が秘められていたと思う。今となっては、マンガ専門書店の店頭でも、それらの作品を見かけることは少ない。環境の変化の前に淘汰されてしまったのだろう。それとも、現代のマンガの中にも変異した彼らの遺伝子は残されているのだろうか。ほとんど今のマンガを読まなくなってしまった私には確かめるすべとてない。
しかし、この本はまずいなあ。あまりにも時代と世代と題材が合いすぎて客観的なレビューが描けない。少なくとも1950年代生まれでないと面白くは読めないでしょう。私も面白いと思う反面、そこはかとないうっとうしさも感じてしまった。あまり昔を懐かしむというのは好きではないのに、こんな題名の本を買ってしまったせいですな。
 これは題名に偽りありで、収められた作品の選者は江戸川乱歩ではない。冒頭に収録されている乱歩の随筆「怪談入門」の趣旨に沿って選んだということになっているが、やっぱりちょっといんちきだなあ。
これは題名に偽りありで、収められた作品の選者は江戸川乱歩ではない。冒頭に収録されている乱歩の随筆「怪談入門」の趣旨に沿って選んだということになっているが、やっぱりちょっといんちきだなあ。
しかし乱歩の選択眼はたしかなもので、今となっては目新しい短編はないが、ほとんど翻訳がなかった時代に自分の読書歴だけを頼りに列挙した作品群は、いまでも十分に面白い。
あまりにも有名なジェイコブズの「猿の手」とか、ビアスの「ふさがれた窓」などは、何度読んでも面白い。
乱歩らしいチョイスでは他には「鏡」の魔力を描いたマクドナルドの「魔法の鏡」や、連続自殺の怪談話、エーヴェルスの「蜘蛛」などがある。乱歩が後者のアイデアを換骨奪胎して無気味な都会の怪談に仕立て上げた「目羅博士」も一緒に収録されている。乱歩自身「怪談入門」の中で改作したとはっきり書いているが、今ならパクリと言われかねないところだが、当時ならセーフだったのだろうか。エーヴェルスの方は蜘蛛の精の色っぽさはなかなかだがファンタジー寄りなので、作品としては乱歩の方が面白さは上。
しかし一番面白かったのは結局、乱歩のエッセイ「怪談入門」だったのが皮肉だ。乱歩は本格推理小説のために尽力した人だが、作風も鑑賞眼も実は怪談ホラー向きだったのではないだろうか。「怪談入門」の中に興味深い一節があったので引用してみよう。
科学小説で通っているウエルズのものを怪談だと云うとちょっと変に聞こえるが、私は昔からウエルズの作風は真に科学心を満足させるものではなく、科学小説の理想型はもっとちがったものである筈だと漠然と考えている。ウエルズのは科学用語を使った幻想小説であって、科学的というよりは寧ろ超科学的であり、英語の所謂シューパーナチュラル、即ち怪談に相違ないのである。
さてさて、星新一や筒井康隆を見いだした大乱歩の考える「科学小説(=SF)の理想型」とはどんなものだったのだろう。
「皇室は今危機に立っている
」という書き出しで本書は始まる。憲法は皇位の継承を「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する
」と定めている。その皇室典範によれば「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する
」のであり、また天皇・皇族は「養子をすることができない
」。
しかし、秋篠宮を最後にここ四十年近く皇室には男子が生まれていない。このままいけば皇室はおろか全ての宮家が近い将来存続不可能となる。なぜこのような危機を招くような法体系を作ってしまったのか。もちろん、戦後GHQも野党も男女平等の観点から「男系のみの皇位継承」に疑問を呈したことはあった。そのときの国務大臣はこう答えたそうだ。
事実問題と致しましては、差し当たり男系の男子たる皇胤が断絶するというおそれがない・・
現在そういう状態に差し迫られていないため、問題を先送りしたわけである。この当時から「先送り」は日本政府のお家芸だったのだ。
125代にもわたって皇位が継承されてきたのは、世界でも稀有のことだろう。いわゆる「万世一系」が簡単に保たれてきたはずがない。実のところ皇位継承の歴史は綱渡りの連続だったようだ。過去には実例があったという「女帝」も、実際は男系を続けるための「つなぎ」であり、緊急避難的なものだったらしい。だから過去の女帝は寡婦または独身であり一代限りであって、女系(女帝の子)の継承はゆるされなかったという。「男が生まれないんだから女帝を認めちゃえばいいじゃん」というような安易なものではないらしい。なにがなんでも男系相続なのだろう。
このように綱渡りのようだった皇位継承を助けたのは、側室の存在だった。近くは桜町天皇から大正天皇まで九代続いて天皇の生母は皇后でなく側室だ。この御側女官=側室制度を止めさせたのは、昭和天皇だったらしい。本書によれば昭和天皇はかなりの人格者で皇室の改革者だったようだ。女官制度の改革についての昭和天皇と生母のあつれきは、戦後のGHQによる皇室制度の大変革とともに本書の読みどころだ。
まあ、よくも悪くも日本の歴史、日本人の精神史に占める皇室の存在の重要性は否めない。この「危機」は果たしてどう回避されるのだろう。それとも。
 中国伝奇の官能的な世界を切れ味鋭い描線が描き出す。
中国伝奇の官能的な世界を切れ味鋭い描線が描き出す。
特に83枚に及ぶ『水滸伝』が圧巻。英雄豪傑もいいが、やはり不貞な悪妻、不埒な悪女たちが色っぽい。流れ落ちるような黒髪と柔肌を包む薄衣がなんとも切り絵の曲線に合うのだ。
洗練の極み。
「女性刑事」 マーク・オルシェイカー (講談社文庫)
マーク・オルシェイカー『女性刑事』(講談社文庫)読了。
ワシントンを舞台にした凄惨な連続殺人。だが、犯人とされた男はすでに死んでいた。次に浮かび上がる容疑者は天才脳外科医。事件を追う美貌の女性刑事は彼に惹かれていくが・・・・
 筋立ては実にうまく、すいすいと読めハラハラドキドキもさせてくれる。名探偵が出てくるような、いわゆる大時代のミステリーと違ってモダンなようだが、しかし、キャラの立て方、ヤマ場の張り方の巧みさは、要するにハリウッド的なのだな。そつのなさが逆に鼻についてしまった。
筋立ては実にうまく、すいすいと読めハラハラドキドキもさせてくれる。名探偵が出てくるような、いわゆる大時代のミステリーと違ってモダンなようだが、しかし、キャラの立て方、ヤマ場の張り方の巧みさは、要するにハリウッド的なのだな。そつのなさが逆に鼻についてしまった。
ただ、真犯人の正体と事件の真相はなかなか意外性があってちょっと新鮮。ミステリというよりSFかホラーのようなアイデアで、一歩まちがうと「トンデモ」になるぎりぎりのところでふみとどまっている。
SF、ホラー好きの私としてはOKだが、それだけに真相解明がラスト近くで、すぐサスペンスフルなクライマックスへ行ってしまうのは逆に不満である。ミステリー的には正しい作法なのだろうが、むしろ真相が判明した段階から、犯人の葛藤・変化・破局をじっくり描いていった方が小説としては、数段面白くなっただろうと思う。どうも、私はミステリーよりSFホラーよりの体質のようだ。
「女刑事」「女探偵」ものは好きなのだが、本書のヒロイン、サンディー・マンスフィールドにはあまり萌えませんでした。美人だし、強烈な濡れ場もあるのだが、なぜだろう。
読んだのは後になってしまったが、先月読了した『名画裸婦感応術』より本書の方が書かれたのは先だ。その分、「知識に頼らず絵に感応する」スタンスがやや遠慮がちかなあ。芸術的体験と霊的体験を同一視する、ややオカルチックな文章が眼につく。
知的で論理的な作品は今日の現代美術というジャンルの作家によって沢山描かれているが、なぜか魂に響いてくるものはほとんどないといってもいいくらいだ。このような作品は「わかる」「わからない」という理由だけで選別される。つまり頭で認識してしまえば、それでいいのである。
(中略)
神は特別の人にしか理解できなような難解な観念など送信してくるはずがない。善人にも悪人にも光が同等に当たるように、誰にも通じる感覚を芸術家の筆を通して描かせるのである。何ひとつ複雑な問題もない。万人が心をオープンにするならたとえ絵の知識がなくても、絵に感動する魂をなびかせるのである。
「神」という言葉を除けば趣旨はありがたい。私のような凡人でも素直な心でのぞめば名画の神髄に触れる可能性もあり、ということだ。
とはいっても、ゴッホ、レンブラントからリキテンシュタインまで、最低限の知識にはちゃんと触れていてくれる。あとは横尾忠則の感応の芸を楽しめばいい。「感応」はもちろん「官能」に通じる。
アルファケンタウリからの旅人「トソク族」と人類とのファーストコンタクトは和気藹々と始まった。しかしトソク族ともっとも親しくつきあっていた天文学者が惨殺死体となって発見されたことから事態は暗転する。なんとトソク族の一人が容疑者として逮捕されてしまったのだ。大統領の命をうけた主人公はマイノリティー裁判に実績のある大物黒人弁護士に弁護を依頼する。前代未聞の「エイリアンが被告の裁判」がはじまった・・・
 前半はSF伝統のファーストコンタクトテーマ、後半は法廷ミステリー。第一長編『ゴールデン・フリース』でもソウヤーはミステリ作家としてもなみなみならぬ手腕の持ち主であるところを見せているが、本書でも法廷ミステリーの部分が面白い。「エイリアンが被告」という異例な裁判だが、検察側も弁護側もかたくなに地球(訴追権を持っている米国カリフォルニア州)の法律の論理にのっとって虚々実々の駆け引きを展開する。
前半はSF伝統のファーストコンタクトテーマ、後半は法廷ミステリー。第一長編『ゴールデン・フリース』でもソウヤーはミステリ作家としてもなみなみならぬ手腕の持ち主であるところを見せているが、本書でも法廷ミステリーの部分が面白い。「エイリアンが被告」という異例な裁判だが、検察側も弁護側もかたくなに地球(訴追権を持っている米国カリフォルニア州)の法律の論理にのっとって虚々実々の駆け引きを展開する。
日本と違って米国は陪審員制度だ。この陪審員を選任する際に原告被告双方の意見もとりいれられるらしいが、弁護側がその作戦を練るところが面白いので引用する。
「じゃあ、だれがいいんです?宇宙マニアですか?」
「それはいい。だが、まず間違いなく検察側に排除されるだろうな」
「スタートレックのファンは?SFファンはどうです?」
「それもいいだろうが、やはり、見え透いている。敵側の標的になるだけだ」
「UFOを見たと思いこんでいる連中は?」
「だめだな──予測がつかない。気がふれている可能性もあるんだから。そういう陪審員は願いさげだ。なにをしでかすかわからないだろう」
スタートレックネタはたくさん出てくるのでファンは読んでいて楽しいだろう。それ以外にも、エイリアン歓迎パーティにスピルバーグが招待されていたり、事件当夜のアリバイがスティーブン・J・グールドの講演会出席だったり、なかなか著者はサービス精神旺盛だ。
地球の法制度とトソク族の法制度は当然違うわけで、エイリアンの視点で「法」そのものを相対化する不条理法廷劇という手もあったと思うのだが、小説はそういう方向には進まない。トソク族も意外なほどあっさりと異星の法制度を遵守する態度を見せて淡々と審理は進んでいく。このまま法廷ミステリとして決着がついてはミステリとしては良しだがSFとしてはなんだぞ、と思っていると、四分の三を過ぎたくらいのところでにわかにSFらしい展開になってくる。
トソク族は生体内部の話に対して地球人が性的な事柄に対するような羞恥心を見せるのだが、これが伏線となっていて、異性人の生理、進化が謎をとく鍵となる。このへんはホーガンの『ガニメデの優しい巨人』を彷彿とさせるところもあるので読み比べてみるのも面白かろう。
ラスト、きちっと法廷ミステリとしての決着もつけ、スペースオペラとしての展開もあり、面白さとしては文句のつけようがない。ソウヤーはやっぱりうまい。この面白さは言ってみればハリウッド映画的なのですな。このままハリウッド映画の脚本になりそうである。その分、軽い面白さであることは否めない。エイリアンが被告の「不条理法廷劇」も読んでみたいと思ってしまったのは、贅沢な感想であろうか。
 どうも昨今の拉致問題その他で、まったくその気のなかった私のような人間まで、そこはかとなくナショナリズムを覚えるようになってきた。そういう気分には違和感を感じる方なので、心のバランスのため手にとったのが本書。
どうも昨今の拉致問題その他で、まったくその気のなかった私のような人間まで、そこはかとなくナショナリズムを覚えるようになってきた。そういう気分には違和感を感じる方なので、心のバランスのため手にとったのが本書。
「民族」とか「国家」とか「伝統」とかは、先験的に「大切なものである」とされている概念だ。日頃は「なぜあるのか」などとは思ってもみない。しかし、考えてみると「民族」も「国家」もあいまいな言葉である。
たとえば「民族」とはなにか。「おなじ文化(特に言語)を共有する人々」というのがおおざっぱな定義だろうが、在日外国人の三世あたりは母国語がしゃべれず、文化的にはまったく日本人だが日本民族とはみなされない。では文化ではなく血縁なのか。わが日本民族の象徴である今上天皇陛下みずからが「桓武天皇の母は百済の人です。だから韓国に親しみをおぼえます」と発言している(日本では小さな扱いだったが英語圏メディアでは大きく報道されたらしい)。
「民族」も「国家」もさほど新しい概念ではない。いってみれば「民族」も「国家」も「想像の産物=物語」にすぎない。それはいわゆる「ナショナリスト(「新しい教科書をつくる会」みたいな人たち)も認めているが、フィクションを前提に「新しい神話」をつくろうという立場らしい。なぜそんな必要があるのだ?と本書の著者たちは疑問を投げかける。
私自身は、少子化の時代、どんどん移民をうけいれて混血し、日本人の遺伝子がもっと雑多になって「新日本人」になってしまうか、日本人自体がなくなってもかまわないのではないかと思っている非国民だ。といいながら、実際は周囲にそれほど国際結婚している人がいるわけでもなく、外国人の友人がたくさんいるわけでもなく、能天気な日本人の観念的意見にしかすぎない。しかし本書の著者たちは、一人は在日韓国人の大学教授、一人は海外生活歴30年で国際結婚している文筆家。知識思想の深さはもちろんだが、やはり日本を相対化する視点が私には全然ないものだ。
単に日本を冷徹に見据えているのではなく、二人とも自分史をきちっと語って、思想形成の過程を明らかにしてくれているので読者にもわかりやすい。森巣氏が海外生活者らしくのびのびと「国家」「民族」から自由になっているのに比べ、姜教授は在日韓国人である出自から、森巣氏のように簡単にはいかなかったようだ。「民族」から自由になる前に、まずアイデンティティとしての自分の「民族」を獲得せねばならなかった事情が、自分史に陰影と厚みを加えている。
ナショナリズムを思想、倫理面だけからでなく、グローバリズムや経済史とも関連させて考察している。なかなか私のような浅学な日本人にはピンとこないところもあるけれど、少なくともナショナリズムはレイシズム(人種差別主義)と不可分であることを忘れないでいようとは思う。
鬼才が極力自らの好みだけで選んだ作家の名画(今回は裸婦がテーマ)を、極力背後の事情を排して絵そのもののみについて語った、絵の話し集。
作家は36人。ピカビア、リチャード・ハミルトン、デ・クーニングなんてとこがいかにも「らしい」チョイスである。私が本書ではじめて知った中ではエドワード・ホッパーの「ある都会の朝」、エゴン・シーレの「夢で見たもの」が素晴らしい。
マネの「草上の食事」やピカソの「アヴィニヨンの娘たち」のような超有名な定番作品もはずしていないが、教科書に載っているような絵の歴史上の価値やエピソードにはあまり触れず、横尾忠則本人が絵から受けた情報を丁寧に素直に語っている。例えば私の好きなクールベの「眠り」(二人の女が全裸で抱き合ってベッドに横たわっている絵)についてこう語っている。
写実主義とは写真のようにリアルに描くという意味ではなく、現実を美化したり理想化したりしないであるがままに描写しようとする態度をいう。(中略)
この女の右手の先がシーツかベッドカバーの所にあるが、指のおかれた場所がまるで切る裂かれた肉の内部のような色をしている。
また巨大な女性器の入り口にそっと触れているようにさえ見える。なんと卑猥な絵であろう。まさに写実主義である。
また、セザンヌの「大水浴図」について語った言葉が、なかなか目からうろこなので、最後に引用しておこう。
美しい女と美しい絵は別である。美しい女性が見たいのか、美しい絵が見たいのかということになると。このセザンヌの女は美において失格である。(中略)
もし美人やセクシーな女を見たいのだったら、別の絵を探してもらうしかない。だからここでは、絵それ自体を見てもらいたいのである。言いかえれば絵の一つ一つの筆のタッチを見て、そこに美を発見してもらいたいのである。もちろん筆のタッチだけでなく線や色彩や構図も、同時にみてもらわなければならないのである。
すると裸の女に美を見つけるように、絵の地肌が俄然美しく見えてきたり、筆のタッチが急に気持ちよく見えて、エロティックに思いはじめるという現象が起こるかもしれない。
もしそうなったらしめたものである。あなたは芸術の眼を手に入れたことになるからだ。
わけあって大急ぎで読んだ、江戸時代に使われた「性的秘語」を網羅した事典。まあ、学術的な書というより、好事本という趣きだ。その手の浮世絵の書き込みや古川柳などでお目にかかった言葉も多かったが、さすがに知らない語もたくさんある。
例えば本書中に頻出する漢字に、人偏にカタカナの「ハ」という(「イハ」)という文字があった。なんと読むのかルビがないので最初は困惑したが、途中で説明している項目があり、疑問が氷解した。これは、なんと「マラ(=魔羅)」と読むのだそうな。
字や語だけでなく、風俗史上の珍しいエピソードも載っている。「水淫」という項目になぜか昭和初期の出来事が紹介されていた。
大阪の料亭に等身大の陶器製女体像の便器を作ったのがあり、その三角地帯に放尿する仕掛けになっていた。事後、像の一方の乳首を押すと冷水が出て、他の一方を押すとぬるま湯が放出され、それが小用後の男のものを三角地帯で水洗したという。しかしこれは間もなく当局から禁止撤回を命ぜられた。
さすがにこんな話はインターネットで検索してもヒットしなかった。このような、知っていてもなんの役にも立たない知識が満載の本だが、なかなか馬鹿にしたものでもない。知らないでいたがために大失敗した先例があるそうな。本書の『帆柱』という項目で、『都の手振り』という文章が紹介されている。
薬ひさぐにや長命、帆柱などの、金字にだみたるふだをかけたり。長命とは不死の薬なるべし、帆柱とは何ならん。もしくは風邪の薬をいへるなぞなぞにゃ、かかるむずかしげなる薬さえその心得て買う人のあればこそ、云々
この文章は戦前「女子高等読本」に江戸の風物を書いた名文として採用されたという。もちろん、これは真面目な風俗エッセイなどではなく、ふざけた戯文である。「長命丸」「帆柱丸」ともにいわゆる強精秘薬、江戸のバイアグラだ。知らないこととは言え、教壇で若き婦女子に大真面目に講義してしまったのだから、当時は大問題になったという。これらの薬や性具秘具を扱う老舗の薬屋の名をとって「四ツ目屋事件」と呼ばれたらしい。
お固すぎても、かえって失敗することがあるという一例ですな。
理に巣喰うは最強の敵――。
房総の富豪、織作(おりさく)家創設の女学校に拠(よ)る美貌の堕天使と、血塗られた鑿(のみ)をふるう目潰し魔。連続殺人は八方に張り巡らせた蜘蛛の巣となって刑事・木場らを眩惑し、搦め捕る。中心に陣取るのは誰か?シリーズ第5弾。
 前作『鉄鼠の檻』に負けず劣らず分厚い。千四百頁弱。膨大な物量は、錯綜するプロットのせいももちろんある。題名通り巧緻に織り上げられたプロットは精密機械のようで、何重にも仕掛けられた言葉やストーリーのトリックはミステリーとして十分に楽しめる。しかしそれらの印象が薄くなるほどの、例によっての主人公京極堂=中禅寺秋彦の薀蓄、饒舌である。
前作『鉄鼠の檻』に負けず劣らず分厚い。千四百頁弱。膨大な物量は、錯綜するプロットのせいももちろんある。題名通り巧緻に織り上げられたプロットは精密機械のようで、何重にも仕掛けられた言葉やストーリーのトリックはミステリーとして十分に楽しめる。しかしそれらの印象が薄くなるほどの、例によっての主人公京極堂=中禅寺秋彦の薀蓄、饒舌である。
今回の饒舌のテーマは主として「フェミニズム」だ。事件の主たる舞台となるのは、規律厳格なる基督教系女学校。主たる登場人物は学園を支配する富豪一族の美貌の母と三人の娘である。この娘の一人が戦闘的フェミニストで、誰一人として論戦で歯が立たない。京極堂をのぞいては。この美貌のフェミニストと京極堂の対話が本書の白眉なのだが、ここが実に面白い。フロイト的男根主義が槍玉にあげられたり、論戦は細部にわたるが、やがて太古の母系社会と男系社会の葛藤にまで話は及ぶ。
このへんまでくると、全編を不気味に操る「蜘蛛」とは「大地母神」のイメージであることが明瞭になってくる。しかし、ミステリー的には全然明瞭にはならない。ラストにいたってもどんでん返しが続き、物語が終わるやいなや、冒頭の章を読み返さざるを得なくなる構造になっている。
ミステリーとしてもすごいのだけど、前作の「仏教」といい本書といい、ミステリー以外の部分の印象が強烈だ。面白かったからいいけど。
超能力探偵榎木津礼二郎がいつもよりまともでおとなしいのがちと物足りない。いつもよりかっこいいけど。
 著者は俳優。『七人の侍』の直情な百姓利吉役や、『赤ひげ』の若い医師森半太夫など多くの黒澤明監督作品に出演している、いわゆる「クロサワ組」の一人。いまの人にはむしろゴジラ映画の方がなじみ深いかもしれない。X星人の頭目だったりゴジラザウルスを助けてゴジラを誕生させた元日本兵といえば思い出す人がいるかもしれない。怪獣映画の派手な役にくらべて黒澤作品では地味な役が多い。しかし一時は黒澤宅に居候していたほど大監督に可愛がられた人らしい。
著者は俳優。『七人の侍』の直情な百姓利吉役や、『赤ひげ』の若い医師森半太夫など多くの黒澤明監督作品に出演している、いわゆる「クロサワ組」の一人。いまの人にはむしろゴジラ映画の方がなじみ深いかもしれない。X星人の頭目だったりゴジラザウルスを助けてゴジラを誕生させた元日本兵といえば思い出す人がいるかもしれない。怪獣映画の派手な役にくらべて黒澤作品では地味な役が多い。しかし一時は黒澤宅に居候していたほど大監督に可愛がられた人らしい。
本書は、その居候していた期間を中心とした「黒澤明との日々」を語るエッセイ集。黒澤明の眼鏡にかない黒澤とウマがあった役者だけに、文章がうまく、きどらない筆致は知性とユーモアにあふれ、なかなか読ませます。
人間黒澤の、魅力もちょっと困ったところも、さすがに起居をともにした人でなければリアルさで書かれている。黒澤明の自伝や他の評論家の評伝からはわからない人間くささが伝わってくる。「無類の肉好きで美食家、月の肉代が百万円を越す」なんていうエピソードは映画と関係ないようで、なんとなく作風に関係ありそうなところが面白い。
とはいっても、やはり面白いのは『七人の侍』から『赤ひげ』にいたる撮影中の思い出だ。映画づくりそのものの話から、黒澤監督はもちろん、三船敏郎、左卜全といった名役者、といえば聞こえはいいが、要するに奇人変人たちのエピソードが抜群に面白い。いつも「不老長寿薬」入りの水筒を首にぶらさげ松葉杖をついている。しかし、バスに遅れそうになると杖をかついで猛スピードで走り出す左卜全などはもう「怪人」の部類だろう。きどったクラブのドアに大石をかついで突進する三船敏郎とか・・まあ読んでもらいたい。書かれているむんむんするような現場の雰囲気は、集団でモノづくりする人々の体臭や哄笑、怒号が聞こえてくるようだ。
黒澤明自身は晩年こそ対談や自伝で自作を語ったけれど、もともと映画以外は人前に出ることをせず舞台挨拶もしなかったらしい。それだけに言われ放題のところもあり誤解も多かったことだろう。著者のような本当に身近にいた人の書く等身大(といっても元々黒澤明は長身だ)のクロサワ像は貴重だ。かといって著者は盲目的なクロサワ崇拝者ではなく、実像を知るゆえの冷静な観察もそこかしこに見受けられる。黒澤映画が好きなので、評論本や評伝みたいのもそこそこ読んではきたが、中では自伝『蝦蟇の油』と本書が突出して面白い。というか他はいらない。
最後に「卜全釣り」の章からちょっと面白いエピソードを引用。
ある女優さんが逃げまどい、矢に当たる場面があり、矢が放たれ見事に当たった。そのときその女優さんが、優しい声で「あっ」といったものだから、黒澤さんは大声で叫んだ。
「違う、違う。本当に当たったときは、もっとギャーとなるだろう。気どってちゃ駄目。もう一ぺん」
ところが、矢は着物の下にとりつけた板をそれて、その女優さんの背中に突き刺さっていたので大騒ぎになった。リアリティとリアルの違いである。黒澤さんの戸惑いは隠せなかった。
もちろん世界のクロサワは戸惑ったままではいない。その後の工夫が章題の「卜全釣り」になるのだが、あとは読んでのお楽しみ。
 澁澤龍彦や三島由紀夫と親交があったということだが、日本にこんな素晴らしい幻想画家がいたとは、寡聞にして知らなかった。しかしフィリップ・K・ディック(『ブレードランナー』や『マイノリティ・リポート』の原作者)の文庫の表紙絵が強烈な印象を残している。左の画像『抽象的な龍』もディックの『ヴァリス』に使われていたものだ。
澁澤龍彦や三島由紀夫と親交があったということだが、日本にこんな素晴らしい幻想画家がいたとは、寡聞にして知らなかった。しかしフィリップ・K・ディック(『ブレードランナー』や『マイノリティ・リポート』の原作者)の文庫の表紙絵が強烈な印象を残している。左の画像『抽象的な龍』もディックの『ヴァリス』に使われていたものだ。
マグリットやダリを連想させるようなモチーフが多いが、彼らより絵はうまくて品がいい。ややグロティスクな風味の前半から、静謐な夢を描いたような後半の作風に移る転機となった大作『聖アントワーヌの誘惑』が圧巻だ。同名のボッシュの作品と同じ地獄図絵だが、さすがにボッシュよりモダンだ。諸星大二郎の世界や、私の大好きなシュールなSFの傑作『シェイヨルという名の星』(コードウェイナー・スミス)の世界を連想させてくれる。
SM雑誌に中川彩子名義では描いたSM挿絵も併載されていた。こちらも上品な画風。中でも、アドバルーンをビルに結びつけているロープの途中に美女が緊縛されている絵が傑作。ビル街の空中に浮かぶ多数のアドバルーンのそれぞれに美女が吊るされている夢幻的な風景は、たしかにSM絵画でありながら、シュールレアリズム絵画と呼びたくなる不思議な絵だ。
「赤い百合」 アナトール・フランス (杉本秀太郎訳/臨川書店)
 実にとんでもない小説である。主人公で、本書の語り手でもあるジャード・クインの肩書きは「犯罪プランナー」。犯罪計画を練り上げ、提携しているギャングの親分に実行させ、自分は多額の分け前をとる。悪党である。それもきわめつけの。クールでシニカル、自分の行為に一切の罪悪感を持たない。女好きだが、女に対する感情はこんなかんじだ。
実にとんでもない小説である。主人公で、本書の語り手でもあるジャード・クインの肩書きは「犯罪プランナー」。犯罪計画を練り上げ、提携しているギャングの親分に実行させ、自分は多額の分け前をとる。悪党である。それもきわめつけの。クールでシニカル、自分の行為に一切の罪悪感を持たない。女好きだが、女に対する感情はこんなかんじだ。
ベッドでのルーは蛇みたいにくねくねと、おれの身体を這いおりたり這いのぼったりする。もちろん彼女は愛しあってるつもりだが、おれにはただのファックにすぎない。
こう書くと、Mr.クインは冷血な二枚目のようだが、語り口は毒舌家で皮肉屋で助平で、結構まぬけなところもある。浮気がばれて妻にブランデーの瓶で殴られ、たいした怪我でもないのに大騒ぎしたり、妻の姉にいいよって股間を蹴られて悶絶したりする。大胆精緻な犯罪を計画しているときとは大違いだ。
犯罪計画といっても、銀行の地下金庫からあざやかに金塊だけ盗み出す、なんていうさわやかな優等生的なものじゃない。罪もない資産家一家をみな殺しにして財産を横領、しかもすべて事故にみせかけるという悪質なやつだ。
ああ、それなのにそれなのに、読み進んでいくうちに、この悪党がどうも憎めなくなってしまう。天才的犯罪計画がうまくいくように願ってしまっている自分に気がつくのだ。なんて不謹慎な。
手口はあざやかというか綿密というか、緻密なのにわざとらしくなく、これならうまくいくかもと思わせる自然さが心憎い。殺し方も結構えぐいのに、躊躇なく淡々と実行されるし描写がしつこくないので残酷さをあまり感じさせない。
こんな話なのに、ラストも変にほのぼのしてハッピーエンドだった?ような読後感が残る、奇妙な小説である。不謹慎といわれても、面白かったのだからしかたがない。



この巻で取り上げられているのは次の16冊。
- 昭和20年『日米會話手帳』小川菊松。
- 昭和21年『完全なる結婚』ヴァン・デ・ヴェルデ。
- 昭和22年『旋風二十年』森正蔵。
- 昭和23年『愛情はふる星のごとく』尾崎秀実。
- 昭和24年『この子を残して』永井隆。
- 昭和25年『宮本武蔵』吉川英治。
- 昭和26年『物の見方について』笠信太郎。
- 昭和27年『三等重役』源氏鶏太。
- 昭和28年『光ほのかに』アンネ・フランク。
- 昭和29年『女性に関する十二章』伊藤整。
- 昭和30年『広辞苑』新村出。
- 昭和31年『太陽の季節』石原慎太郎。
- 昭和32年『挽歌』原田康子。
- 昭和33年『経営学入門』坂本藤良。
- 昭和34年『論文の書き方』清水幾太郎。
- 昭和35年『性生活の知恵』謝国権。
- 昭和36年『英語に強くなる本』岩田一男。
いまでも有名な本も、すでに忘れられてしまった本もある。いまだに読みつがれているのは「宮本武蔵」くらいか。私が完読したことがあるのは「武蔵」と「完全なる結婚」の二冊だけ。「広辞苑」も持ってるけど、これを完読した人は少ないだろう。
別に自分で読んだ本があまり取り上げられていなくても、本書は面白い。なぜなら、「戦後のベストセラー本史」ではなく「ベストセラーによる戦後史」だからだ。マッカーサーに「四等国」と決めつけられた日本が、なんとか2.5等国ぐらいまで持ち直していった時代の姿が、年ごとのベストセラーになった本の事情から垣間見えてくる。
たとえば最初の『日米會話手帳』の発売は昭和二十年九月十五日。大日本帝国の敗戦からちょうど一ヶ月めだ。
八月十五日正午の天皇の重大放送が終わった途端、大日本帝国がただの日本国として新生したわけではない。(中略)アメリカ軍に対する日本人の感情も「鬼畜」から「ハローハロー」に変わるまで、ある時間を必要とした。(中略)九月十五日前後は、ちょうど「鬼畜」が「ハロー」に変わる境目だった。そこへこの本が出たのだから、これは売れない方がどうかしてる。
内容と言えば、ただ簡単な日常会話が七十九例、英単語が百七十三語載っているだけのペラペラの小冊子だったらしい。それが三ヶ月間に三百六十万部も売れたのだ。「英会話」でなく「日米会話」だったところも時代を現している。
戦争中は敵国語として英語の使用を禁じられていた一億日本人がこの本のおかげであっというまに自在に英語をあやつるように・・ならなかったのは本書の最後が『英語に強くなる本』であることでもあきらかである。戦後十六年経っても日本人は全然「英語に強く」なっていなかったわけだ。
この章では著者(井上ひさし)がオーストラリア国立大学(ANU)で日本語学科のレジデントをしていたことが語られる。そこで著者は「なぜ日本人が英語に弱いか」という積年の疑問の答えを見つける。少し長くなるが興味深いので引用してみる。
ANUの学生の勉強ぶりには圧倒された(中略)彼は和英辞典を片時も左手から離そうとしない。(中略)あまり頻繁に引くものだからページが上下にめくれあがって、まるでキクラゲの束を持っているようにみえた。彼はその辞引を左手だけで引きまくった。そしてその引き方の素速いこと。彼は三年半で辞引を一冊、まさに引き潰そうとしていたのである。彼は五キロほど離れた住宅地からホンダのオートバイで通学していたが、往復の途中は実況中継のアナウンサーになった。自分の目に見えてくるものを次々に日本語で言いたてるのである。彼が準備中の卒業論文は黒澤明論であり、黒澤映画のシナリオ、たとえば『生きる』や『七人の侍』をほとんど暗記していた。そこで週一回の会話の時間には、日本政府はなぜ黒澤明に出資しないのかとか、東京になぜ「黒澤明通り」がないのかとかいった難問を浴びせてきた。
ひるがえって日本の事情を見るに英文科学生が(中略)結論は一つしかない。われわれ日本人は語学が不得手なのではない。それは怠け者の遁辞であって、つまるところ私たちの大半はいい加減な勉強しかしていないのである。(中略)言い添えておくと彼は特別な秀才ではない。ただの普通の学生である」
ちなみに『英語に強くなる本』がベストセラーになるに力があったのは前書きの「手洗いにいいるとき、外から叩かれたら何といったらいいだろうか」とう設問だったそうな。答えの「Someone in」は流行語になり、『英語に強くなる本』の代名詞になったという。
他の本を扱った章でも、「あれから三十年経つが事情はあまり変わっていないようだ
」(論文の書き方)とか「この難問を提示している『女性に関する十二章』や『文学入門』は、まだ少しも古びていないことになる。
」といった著者のフレーズが頻繁に出てくる。まだ全然「戦後は過去のものになって」いないのですな。
たまたま硬めのところを取り上げたけれど、『太陽の季節』では今をときめく石原都知事の颯爽としたデビュー時の様子、『経営学入門』ではあの長島茂男登場の衝撃が書かれ、ストリップ劇場でスクリプトを書いていた著者の青春の思い出など「愉快な戦後史」もたっぷりの十分にエンターテインメントな一冊だ。
なかで感動的なのはゾルゲ事件の尾崎秀実が妻とかわした書簡集『愛情はふる星のごとく』についての章。転向と直言の両義性をゾルゲの書簡に見る著者の読み方は深読みだろうか。これは現物を読んでみたくなる。
取り上げられているのは次の十八冊。
- 昭和37年『易入門』黄小蛾。
- 昭和38年『危ない会社』占部都美。
- 昭和39年『愛と死を見つめて』河野実/大島みち子。
- 昭和40年『おれについてこい!』大松博文。
- 昭和41年『人間革命』池田大作。
- 昭和42年『マクルーハンの世界』竹村健一。
- 昭和43年『どくとるマンボウ青春記』北杜夫。
- 昭和44年『都市の論理/知的生産の技術』羽生五郎/梅棹忠夫。
- 昭和45年『心 いかに生きたらいいか』高田好胤。
- 昭和46年『日本人とユダヤ人』イザヤ・ベンダサン。
- 昭和47年『日本列島改造論』田中角栄。
- 昭和47年『恍惚の人』有吉佐和子。
- 昭和48年『日本沈没』小松左京。
- 昭和49年『ノストラダムスの大予言』五島勉。
- 昭和50年『欽ドン』萩本欽一。
- 昭和51年『四畳半襖の下張裁判・全記録』丸谷才一。
- 昭和52年『間違いだらけのクルマ選び』徳大寺有恒。
 「戦後史」からだんだん「昭和史」という感じになってきた。十八冊のうち、私が読んだことがあるのは、『どくとるマンボウ青春記』『知的生産の技術』『日本人とユダヤ人』『日本沈没』の四冊のみ、ベストセラーにはあまり縁のない読書傾向なのが証明されたようでうれしい。ベストセラーを全部読んでるのって、なんだかかっこ悪いではないか。
「戦後史」からだんだん「昭和史」という感じになってきた。十八冊のうち、私が読んだことがあるのは、『どくとるマンボウ青春記』『知的生産の技術』『日本人とユダヤ人』『日本沈没』の四冊のみ、ベストセラーにはあまり縁のない読書傾向なのが証明されたようでうれしい。ベストセラーを全部読んでるのって、なんだかかっこ悪いではないか。
今回は前巻に加えるような感想は特にない。取り上げられている本の善し悪しではともかく、戦後史としては、前巻の方が興味深い。これは時代そのものの面白さが違うのだからしかたがないだろう。
なかでは、「外国人による日本人論」を、著者の井上ひさしが比較考察している『日本人とユダヤ人』の章が面白い。西洋人による日本人論の元祖はなんといってもフランシスコ・ザビエルだが、彼の書簡はおおむね日本人に好意的のようだ。
日本人は総体的に良い素質を有し悪意がなく交わってすこぶる感じが良い。(中略)日本人はたいてい貧乏である。しかし武士たると平民たるとを問わず貧乏を恥辱だと思っているものは一人もいない。(中略)大変心の善い国民で交わりかつ学ぶことを好む。
ところが、鎖国時代の江戸期に、唯一、長崎出島で幕府役人たちと接していたオランダ人たちの日本人に対する印象ははなはだ良くない。
礼儀を重んじるくせに狡猾で抜け目がなく嘘つき
と、こきおろされている。このオランダ人の日本人観が世界中に流布したらしい。
しかし、黒船でやってきて下田に上陸したハリスは、滞在日記にこう書いている。
私はくっきりとして美しい日本人の姿が好きである。人民の身なりはさっぱりしていて立居振舞いが優雅である。世界のあらゆる地方の貧乏に何時でも付き物になっている不潔さが少しもない。(中略)彼らは喜望峰以東のいかなる人民にも優っている。
ほとんどべたぼめである。同じ、日本人と接することのあった外国人が、なぜこれほどに正反対な日本人観を持つのか。著者はこれを簡単に二分する。
庶民とつきあう機会が多かった人たちはザビエルやハリスのような「良き日本人」観を持つ。庶民とあまり交流のない軍人や政治家や学者は「幼稚で野蛮、尊大で狡猾、神経質で昂奮しやすい」という「悪しき日本人」観を持つ。
なかなか明快ですな。庶民といってもおもに明治以前の庶民のようだが、それでも日本の庶民のはしくれとしては気持ちがいい。
たしかに、昔から日本は庶民で持ってる国なんだね。敗戦のどん底からこれだけの経済成長をとげたのも、結局は無名の庶民が勤勉によく働いたからで、官僚や政治家の貢献度は1%もあるまい。(マイナスはあったかもしれないが)
それともう一つ思ったのは、日本人は「貧乏」が得意なのだ。バブルのときのように、にわか金持ちになると醜さを露呈するが、貧乏なときは西洋人が感心するほどきりりと身持ちが良くなる。なんだか誇らしいような情けないような複雑な気持ちになりますわな。
最近、喜寿の父が井上ひさしのエッセイを気に入って、よく図書館で借りてくくるので、面白そうなのはお相伴にあずかっている。
本書の対談相手は俵万智、ミヒャエル・エンデ、山口昌男、佐高信、山田詠美等々。しかし、私のお目当ては黒澤明との対談のみ。他は申し訳ないが、流し読みでパス。
ホストの井上ひさしが黒澤明の信奉者なので、丁々発止とはいかないが、さすがに黒澤映画をよく観ているので、監督も機嫌よく名作の裏話を語りまくる。分量も黒澤の回だけ他の倍以上ある。黒澤明ファンにはたまらない話が満載である。私の下手な紹介や感想より、さわりを引用してみよう。(EP2が明日から封切りの)スターウォーズにも言及している。
僕はアメリカの映画音楽はちょっと問題だと思うんです。たとえば『風と共に去りぬ』なんてベタでしょう。うるさいんですよ。音楽というのは、入れないで、あるとこでスウッと入ってくるから効果があるんで、ベタに説明的な音楽が入っていたらマイナスだと思うんです。それについてルーカスともずいぶんやり合いました。『スターウォーズ』でも音楽が入りすぎていると言ったら、ルーカスは、あの作品は子どもが観るから、わかりやすいように音楽をベタに入れたんだというので、そのとき僕は、それはあんた違う、それは子どもを侮辱している。子どもはそんなことしなくてもよくわかるんだと、ずいぶんやり合ったんですよ。
井上ひさしが「『七人の侍』の、しいたげられた百姓に味方する『黒澤ヒューマニズム』が僕らをつくった」と言うと、これに対する黒澤の答えが意外なものだ。
『七人の侍』をつくって、百姓を欲張りだとずいぶん批判的に描いた。ところが、実際に撮影を田んぼでやったんですが、百姓たちの地主といろいろ交渉していたら、まだ書きたりないという感じがした(笑)。
欲たかりなことはものすごいんです。馬が鎌を蹴飛ばして曲がっちゃったんで弁償するからといったら、これは先祖伝来なものだと(笑)
井上ひさしの感動のもっていきばがない。なかなかそんな「しいたげられた農民像」みたいな教条主義的な見方では映画は作っていないぞ、ということなのだろう。
他にも、映画に限らず、モノを創るのが好きな人には、モノ創りの天才の飾らない話しぶりと話の内容は、興味深いことこのうえないはず。
最後に二人は日本の映画製作・配給の現状に対して悲憤慷慨するのだが、この対談の初出は一九八八年だ。現在はその頃よりシネコンの類いが増え、映画館なども立派になったように感じるが、井上ひさしの次のような話を聞くとどうだろう。
僕が唯一詳しい外国であるオーストラリアを例にとりますと、「日本より下」などと日本人は思っているようですが、映画館や劇場はとても勝負になりません。清潔なトイレ、明るいロビー、座席は広くて、床はジュータン。ちなみに座席はリクライニング・シートです。上映前にちんけなCMなどやりませんし、案内嬢はロングドレスで正装、とても親切。観客も絶対に紙袋をがさがささせたりしませんし、ま、比較するさえ無意味です。
この文章から十五年経つわけだが、さて日本の映画環境はオーストラリアに追いついたのだろうか。
<前 | 日付順目次 | 書名索引 | 著者名索引 | 偏愛選書 | 次>
 ところで、本書の表紙はいわずとしれた生頼範義画伯だ。決して悪くはないし、私は好きだが、本書の中身はこれほど濃くはない。
ところで、本書の表紙はいわずとしれた生頼範義画伯だ。決して悪くはないし、私は好きだが、本書の中身はこれほど濃くはない。