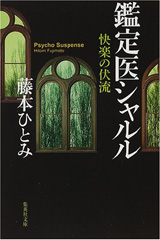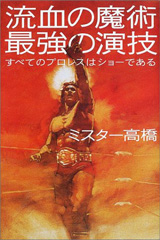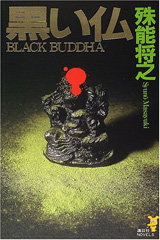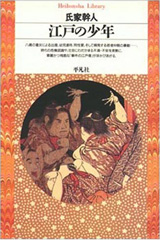◆ 歯皮膚屁本 - はひふへほん ◆ HOME
<前 | 日付順目次 | 書名索引 | 著者名索引 | 偏愛選書 | 次>
読書日記 2002/01-06

 −元祖スターウォーズ
−元祖スターウォーズ
いわゆる「スペースオペラ」の古典中の古典。「レンズマンシリーズ」の記念すべき第一作及び第二作。私も高校生の頃にはじめて読んだときは「世の中にこんな面白い小説があったか」と耽読しましたが、今再読してみると、さすがに古色蒼然としていることは否めない。
科学的設定の旧さはまあしかたがない。旧いなりに綿密な書き込み、ガジェットの面白さはさすがに旬の作家の力の入った仕事である。古いなあと思わせるのは主人公キニスンの優等生的キャラクター設定だ。自分の軍事任務にまったく疑問を持たず、超人的活躍を見事にこなし、決して奢らず謙虚で友情に厚く女性に固い。友人としてはともかく、小説の主人公としてはいささか面白みに欠ける。
キニスン以外の人物も善悪の書き分けは単純だ。善側の登場人物はすべて善人で、悪側は一部の改心する者を除いて徹底的に悪人である。複雑な悪の哲学を持っていたり屈折して心ならず悪の道に進んだ者など一人も登場しない。逆にその単純さが魅力的なSF的設定と相まって、安心して読める単純な面白さを保証してくれるとは言える。
「魅力的なSF的設定」は色々ある。そのほとんどはSFの定番的設定になっている。映画「スターウォーズシリーズ」の設定を本書と比較してみるとよくわかる。
エリート戦士。SWではジェダイの騎士。レンズマンではずばり「レンズマン」。
宇宙人老師。SWではヨーダ。レンズマンでは哲学的龍であるアリシア人。
光の武器。SWではライト・セーバー。レンズマンではレンズ。ともに光り輝き、持ち主の精神エネルギーを受けて稼働するフォースの象徴である。
善悪二元論。SWではジェダイの騎士とシスの暗黒卿。レンズマンではアリシア人とエッドール人。
混成文明。両作品の善悪文明ともに多様な異星人が混在して成り立っている。しかし指導的人種はなぜかどちらも地球のアングロサクソン系である。
超人の血。SWの「フォース」、レンズマンでは「精神エネルギー」。どちらの主人公もこれらの超能力が飛び抜けて強い。しかしどちらも一代では完成せず、能力の強い主人公たちが恋愛して生まれた子供たちがさらに強い超能力を持って、物語を大団円に導く。
スターウォーズはビジュアルイメージの部分でクロサワ映画の影響が強いことは有名だが、こうしてみると物語の骨子はアメリカの伝統的スペースオペラの系譜のもとにあることがよくわかる。だからこそ「スターウォーズ」第一作を25年前に観たとき、「これだよ!こういうのを見たかったんだよ」と若きSFファン(私だ)の血が沸騰したのもむべなるかな。
女子プロレス界を舞台にハードボイルドミステリを展開した『ファイアボール・ブルース』の続編。
前作と異なり今回は短編連作形式。ミステリ的要素も少なくなり、より女子プロレス界の内幕もの、青春ものとしての色合いが濃くなっている。
引退した主人公が昔の仲間たちと再会するラストはなかなか感動的だが、全体に前作ほどの凝縮力はない。前作ではプロレスは背景で、業界外の犯罪がミステリを構成していたが、本書はもろにプロレス物語である。プロレスが真剣勝負であることを前提とした小説は、今となっては存在はゆるされないのではないかなあ。
前書きのエピソードによれば、著者は教え子である大学の新入生からこんな質問をされたという
「先生の講義を聞きたいと思ったのですが、母から、浮世絵なんていやらしいから止めなさいと注意されました。どのような内容になるのですか」と、真顔で聞かれたのである。
実は私自身も学生の頃、卒業論文に浮世絵を扱うと言ったところ、母親から「せっかく大学に入って浮世絵ですか」とがっかりした口調でつぶやかれたことがある。
 本書はこのような世間的風潮(というのも過去のものだと思うのだけど、本書は今年が初版なのである)をただして、正しい浮世絵の姿を伝えようという動機で執筆された。当然、内容は初歩的である。網羅的で総括的で、春画から制作システムまで気を配っている。まさしく入門書としは最適。目新しい話はないが、江戸人たちにとって「浮世絵」がどういう意味があったかという視点から書かれているので、知識羅列的でない面白さはある。三大浮世絵師、北斎・広重・写楽それぞれの著者評も斬新ではないが的確だ。
本書はこのような世間的風潮(というのも過去のものだと思うのだけど、本書は今年が初版なのである)をただして、正しい浮世絵の姿を伝えようという動機で執筆された。当然、内容は初歩的である。網羅的で総括的で、春画から制作システムまで気を配っている。まさしく入門書としは最適。目新しい話はないが、江戸人たちにとって「浮世絵」がどういう意味があったかという視点から書かれているので、知識羅列的でない面白さはある。三大浮世絵師、北斎・広重・写楽それぞれの著者評も斬新ではないが的確だ。
鈴木春信の美人画で有名な笠森お仙という美人がいた。谷中の水茶屋の看板娘。現代ならウェイトレスのような目立たない職業の女性がクレオパトラや楊貴妃のように何百年も名を残す。浮世絵の威力と江戸の庶民の文化的パワーがうかがい知れるというものだ。そのお仙と並び称せられたのが浅草寺裏の楊枝屋の娘本柳屋お藤。大文人の大田南畝までが「阿仙阿藤優劣弁」という戯文で二人のどっちが美人かを論じていたというのだから、さすがに江戸人は風流?である。
春信はお藤も描いている。どちらの錦絵も評判になって飛ぶように売れたらしいが、お仙もお藤も絵の上では見分けがつかないところがおかしい。どちらも典型的な春信美人で二人の個性などはどこにもない。これは歌麿も北斎も国貞も同じで、一人写楽のみがモデルの個性に肉薄する大首絵を描いた。しかしその「個性の絵」が世に受け入れられたとは言い難い。江戸人も春信美人歌麿美人という美の記号を実在の人物に見立てることで十分に楽しむことができたのだろう。
これを読んで思ったのだが、この江戸人の美人画の見方と浮世絵の美人の記号性の伝統は現代のマンガにまで連綿と続いているのではないか。一人の漫画家の描くヒロインの顔は何パターンもない。へたをするとみな同じ顔である。手塚治虫も石森章太郎もヒロインは手塚美人に石森美人。サイボーグ003はフランス人のはずだが、佐武と市捕物控に同じ顔で出ても違和感はあるまい。
昔の作家はしかたがないにしても、最近の作家ではうまい方なのかな、浦沢直樹の『Monster』も冒頭出てくるドイツ娘がどう見ても猪熊柔と変らないぺったんこ顔なのにはまいる。話は面白いのだが読み続ける気力がちょっと萎えた。
なぜならマンガ界にはすでに大友克洋という「写楽」がいたからだ。最近あまりマンガを読まなくなってしまった私だが、大友後のマンガ家はみなあのラインをクリアしているような思いこみがあったのだ。しかし、やはり大友は写楽のような天才であり、線描や上っ面を真似るエピゴーネンはたくさん出ても、あの「外国人から見た日本人」を描けるマンガ家は簡単に出るものではないのですな。
エウリピディスのギリシャ悲劇を題材にしたフランスの古典劇。いずれもいわゆる「三一致の法則」に忠実な端正な戯曲である。
「フェードル」はローマ建国の英雄テセウスの后。義理の息子イッポリテは処女神アルテミスに忠誠を誓った超真面目男。アルテミスと犬猿の仲の愛欲の女神アプロディテが愛欲を嫌悪するイッポリテに呪いをかける。道具に使われたのが継母のフェードル。義理の息子に禁断の恋情をいだき言い寄るがすげなくふられてしまう。心乱れたフェードルは夫に息子に言い寄られたと讒言してしまったので、さあ大変。
「アンドロマック」はトロイア戦争のトロヤ方のヒロイン。アキレスに殺される英雄ヘクトルの妻である。トロヤ陥落後、敵将ピュロスの奴隷になるが、ピュロスは彼女を奴隷として扱わず、正式に求愛する。しかしアンドロマックは夫への愛は変わらないとして拒絶する。拒絶されたピュロスはますますのぼせあがって、結婚してくれればアンドロマックの息子を自分の子供として育て立派な武将にしてみせるが、断れば息子の命はない、と彼女をおどす。
この二人のドラマだけではなく、ピュロスには昔からの婚約者ヘルミオネがいて、さらにヘルミオネに恋い焦がれているオレステスという勇者がいる。舞台は次々とこれらの不毛なカップルが現われて恋情をもやし嫉妬し拒絶するさまを演ずる。
これだけ劇的な設定なのだから面白くないわけがなく実際面白いのだが、どうしても登場人物がギリシャ神話やギリシャ悲劇の古代人たちには見えない。17世紀フランスの宮廷人たちで有る方が似合う。どう考えても、あの好色神ゼウスの子たちが、わがものとした未亡人に悠長に求愛なんてしてるわけがない。
「生命進化8つの謎」 ジョン・メイナード・スミス & エオルシュ・サトマーリ (長野敬訳/朝日新聞社)
 なんとも安っぽい邦題だ。原題は「THE ORIGINS OF LIFE」だからズバリ「生命の起源」だ。せめて「生命進化の八段階」ぐらいにできなかったものか。
なんとも安っぽい邦題だ。原題は「THE ORIGINS OF LIFE」だからズバリ「生命の起源」だ。せめて「生命進化の八段階」ぐらいにできなかったものか。
著者の前作『進化する階層』の「平易な紹介」とのことだが、どうしてどうして、私のような素人には歯ごたえがありすぎる内容だ。要点を訳者あとがきから引用してみる。
進化における複雑さの増大は、一連の大きな<進化的な移行>の結果として達成されてきた。移行には、情報が貯えられ、伝えられてゆく方法の変化が関係している。
生命の発生から、言語の未来までの長い長い進化の全歴史が対象になっているが、恐竜はもちろん地質時代表も出てこない。
アミノ酸のスープ→染色体→細胞→真核細胞→性の誕生→多細胞生物→動物→人類→言語、という色々な段階での生物構造の移行がこと細かに書かれる。前半は難解で、巻の最後に近づくほど読みやすくわかりやすく一般的には興味深い内容になってくる。しかし、本書の真骨頂は前半の細胞レベルの進化の考証にあると言っていいだろう。ちょっと残念だが。
連なったアミノ酸が自己を複製することが生命の端緒であるのなら、実際にどのようなメカニズムで複製が行われるのか。ミトコンドリアのような細胞内器官は、太古には別の生命体だったのが細胞内にとりこまれて共生したのだとするなら、いかにしてとりこまれ、どんなしかけで細胞融合がおきたのか。従来の生物学の啓蒙書でなんとなく省略されてきた細部について、しつこくしつこく書き込まれている。
正直、「生命進化の驚異に感動する」というような簡単な読み方ができるような本ではない。文章も読みやすくない。そのかわり「進化について考えている専門家はここまで考えているんだ」ということがおぼろげに見えてくるような気がする。
再読しないとほとんど頭に残っていないなあ。
私たちの世代で、百姓一揆と言えば白土三平の『カムイ伝』や『忍者武芸帳/影丸伝』で描かれた「虐げられた民衆の抵抗手段」としての「聖なる」百姓一揆だ。しかしそのような、いかにも「マルクス史観的一揆像」は最近では全否定されないまでも、かなりの修正を迫られているようだ。
新しい流れの一揆研究の入門として代表的な一冊と言えるのが本書だ。白土三平ファンとしてはおそるおそる読んだというのが正直なところだが、思ったほど白土一揆観を否定するような内容ではなかったのでホッとした。
なにより一揆といっても多様な形態があったというのが、あたりまえだが印象的。ムシロ旗を押し立てて竹槍や鎌・鍬などの農機具で藩の武装兵と死闘を繰り広げるのが一揆だと思っていたが、実際にはそのような「武装蜂起」より、村をあげて他領に逃げ出す「逃散」が多かったらしいこと。一揆にも藩との暗黙の了解的作法があり、それにのっとっている限り藩も一方的な弾圧はできなかったこと。等々。
白土史観とはだいぶ違うなあとは思ったが、戦国時代を舞台にした『影丸伝』はともかく、『カムイ伝』を読み返してみると一揆の過程もかなり詳細に描いている。「逃散」もちゃんと登場する。白土三平が単純な武装蜂起ばかりを描いていないことにいまさらながら気がついた。白土ファン失格。後ればせながら気がついたのも本書のおかげである。
 もちろん『ドラキュラ戦記』に続くシリーズ第三作。前作では登場しなかった四百歳の美少女吸血鬼ジュヌヴィエーブ・デュドネも大活躍する。吸血鬼を次々と殺害してゆく「真紅の処刑人」と対決し危機に陥る。
もちろん『ドラキュラ戦記』に続くシリーズ第三作。前作では登場しなかった四百歳の美少女吸血鬼ジュヌヴィエーブ・デュドネも大活躍する。吸血鬼を次々と殺害してゆく「真紅の処刑人」と対決し危機に陥る。
今回はドラキュラ成婚にわくローマから物語が始まる。歴史とデカダンの都を舞台に闇の世界を跳梁する勢力の暗闘が描かれるのだが、背景は絢爛たる「映画の都」としてのローマだ。「007=ジェイムス・ボンド」を筆頭にめくるめく映画のパスティーシュイメージが氾濫する。まさしく『フェリーニのローマ』だ。
ドラキュラを上回る恐ろしい怪物、本書最大の敵役のイメージが、大好きなフェリーニの映画のこわいこわいキャラクターが使われていることに気づいたときは狂喜しました。前二作を読んだ人は絶対の買い。まあ、私がいうまでもないだろうが。
ところで気になるのはシリーズの行方。ドラキュラが死んだのだから、当然終わりだろうって?・・・・どうやらそうでもないらしいのだ。さすがはアンデッド=ドラキュラである。
「鑑定医シャルル」シリーズの第一作(先に読んでしまった『歓びの娘』は第二作)。第一作だけに美貌の鑑定医シャルルのクールさニヒルさもまだ中途半端。なにしろ本書のヒロインである女性捜査官と恋仲らしきものになるのだ。
二人が捜査するのはパリで起きた連続強姦殺人事件。被害者はいずれも亜麻色の髪の女性で、現場には焼いた胡桃など奇妙な遺留品が残されている。捜査の場面と交互に、犯人らしき人物の同性愛者めいた日常場面がカットバックで挿入される。
意外な犯人の意外な正体と、その倒錯した動機、。ミステリーとしての面白さは中程度というところか。犯人像と動機の解明にフロイト流の精神分析手法で味つけされているが、わざとらしくなってないのは、十二分に著者が勉強しているせいでしょう(と解説の福島章先生が太鼓判を押している)。
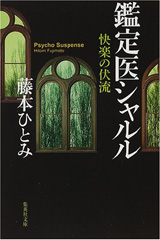 「鑑定医シリーズ」の第三作。『見知らぬ遊戯』で恋人になったアニエスは前作も本作もまったく姿を見せない。別れてしまったのか?
「鑑定医シリーズ」の第三作。『見知らぬ遊戯』で恋人になったアニエスは前作も本作もまったく姿を見せない。別れてしまったのか?
第二作ではシャルルにはまったく女の影はなかったし、少女娼婦の誘惑にも動じなかったが、本書のヒロインの女性司法官とはなかなかいい雰囲気になる。年頃の息子もいる中年女性だが、マザーコンプレックスのシャルルにはかっこうのお相手ではある。
今回の事件は老婆ばかりを狙う連続殺人だが、えぐさと猟奇度ではシリーズ随一だ。先天的凶悪犯罪者は出てくるは、娘、婿、孫、すべての家族を支配するグレートマザーは出てくるは、もりだくさん。犯人の意外性はないけれど、ちゃんとクライマックスには別のサプライズも用意されている。しかし、もう一人の犯人の動機はさすがに少し苦しい。
家族が崩壊してはじめて家族の真実に気づくヒロインがせつない。
前作『ドラキュラ紀元』は元祖吸血鬼小説=ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』のラストを逆転させ「ヴァン・ヘルシング教授がドラキュラに敗れた」世界を描いたホラー小説の大傑作だ。
イギリス全土はドラキュラに征服され、英国人は次々と吸血鬼に転化させられていく。その治政下で、吸血鬼の娼婦ばかりが惨殺されるという事件が発生。闇内閣<ディオゲネス・クラブ>のエージェント、ボウルガードは連続殺人犯<切り裂きジャック>の追跡に乗り出す。一方、ドラキュラとは血統を異にする吸血鬼、実年齢は472歳だが外見は16歳の美少女ジュヌヴィエーヴも事件を追いはじめる・・。
舞台設定も魅力的だが、虚実ないまぜの登場人物が次々とあらわれる才気あふれるストーリーテリングが素晴らしい。歴史上の有名人はもちろん、小説・コミック・映画といった架空世界の登場人物たちが、そのキャラクターをいかした活躍を展開する。そう、山田風太郎が得意にして「明治もの」で展開した手法ですね。なにしろモロー博士とジキル博士が怪しい実験をしている同僚なのだから、ホラー好きSF好きにはたまらない。
 続編の本書でも、そのへんの魅力はまったく失われていない。
続編の本書でも、そのへんの魅力はまったく失われていない。
イギリスを追われたドラキュラが今度征服したのはドイツ。そしてイギリスとその友邦に報復を開始する。両陣営ともに吸血鬼と人間(この世界では「温血=ウォーム」と呼ばれている)の混成軍がまさに血で血を洗う「第一次世界大戦」。いまや闇内閣の重鎮となったボウルガードやその部下であるウィンスロップが戦火を縫って活躍する。今回は登場しないジュヌビエーブにかわってけなげに働くのは吸血鬼ジャーナリストのケイト・リード。ドイツ側の狂言回しをつとめるのは英雄リヒトホーフェンの伝記作者として雇われたエドガー・アラン・ポー。やがてドラキュラの秘密兵器、吸血鬼戦闘航空団がその正体をあらわす・・。
この「吸血鬼戦闘航空団」の描写だけでも本書を読む価値は十分にある。ただし、吸血鬼(にもいくつか種類がある)と人間が共存している世界があたりまえのように描写されるので、前作『ドラキュラ紀元』を読んでなかったら、まずはそちらから読むことをおすすめ。
 今月のラインナップ中、唯一血みどろでない一冊。借りて読んだので現在手元にないため、詳しいレビューが書けない。のでAmazonnのレビューを引用する。
今月のラインナップ中、唯一血みどろでない一冊。借りて読んだので現在手元にないため、詳しいレビューが書けない。のでAmazonnのレビューを引用する。
「あたくし、象を見ると耳鳴りがするんです」退職判事関根多佳雄が博物館の帰りに立ち寄った喫茶店。カウンターで見知らぬ上品な老婦人が語り始めたのは、少女時代に英国で遭遇した、象による奇怪な殺人事件だった。だが婦人が去ったのち、多佳雄はその昔話の嘘を看破した。蝶ネクタイの店主が呟く彼女の真実。そしてこのささやかな挿話には、さらに意外な結末が待ち受けていた…。(表題作)ねじれた記憶、謎の中の謎、目眩く仕掛け、そして意表を衝く論理!ミステリ界注目の才能が紡ぎだした傑作本格推理コレクション。
主人公は『六番目の小夜子』の主人公の父親。収められた短編はいずれも端正で上品な仕上がり。犯罪の匂いが全然しない話からいつのまにか巧緻な犯罪がひそかに姿をあらわす、という私の好きなパターンの、しかも上出来な短編が多い。
ミステリーは好きだが、暴力や残酷な場面はきらい、現実ばなれした凝りすぎたトリックや大仰な名探偵も興ざめ、という人にはかなりおすすめ。
 あらすじは裏表紙のあおりを引用する。
あらすじは裏表紙のあおりを引用する。
忽然と出現した修行僧の屍、山中駆ける振袖の童女、埋没した「経蔵」…。箱根に起きる奇怪な事象に魅入られた者―骨董屋・今川、老医師・久遠寺、作家・関口らの眼前で仏弟子たちが次々と無惨に殺されていく。謎の巨刹=明慧寺に封じ込められた動機と妄執に、さしもの京極堂が苦闘する、シリーズ第四弾。
被害者の僧侶たちがなぜ殺されねばならなかったのか。
著者はその謎を前にして、仏教史と禅をめぐる膨大な蘊蓄と難解な議論を登場人物たちに展開させる。議論というより「問答」といったほうがいいか。しかし、これが実に面白い。なにしろ、禅は言葉による理解を否定している。「悟り」のような神秘体験を神秘体験としてでなく小説にどういかすのか。この難事業を、なんと著者はこの小説で「成功」させている。
ラストで明らかになる犯人はさほど意外ではない。そのうえ動機が突拍子もないと感じるむきもあろう。その動機に説得力をもたせるためのあの物量だったのか、とも思えるが、やはり、蘊蓄と議論こそが本書の骨子であって、殺人は、まあ枝葉でしかない。京極堂と犯人の対決シーンも、犯罪を暴くというより「禅問答」に終始する。
本書のテーマは「殺人事件」ではなく「仏教」なのだ。
だから、このへんを楽しめないと、本書の膨大な分量はちと苦痛かも。なにしろ長い。文庫版で千三百四十頁。しかも波瀾万丈のストーリーというわけでもない。
それでも、これだけの長さをなんとか読み進められるのは、ひとつにはキャラクター設定の面白さゆえだろう。
主人公の古本屋陰陽師の京極堂や超能力探偵榎木津の奇人ぶりもさることながら、今回は初登場の山下警部補がおいしい。はじめは頭が固い警察官僚という典型的な敵役キャラとして登場する。しかし経験や常識がまったく通用しない怪事件に翻弄されるうちに、自分や警察の捜査に哲学的な疑問を持ち、使い物にならないほど落ち込んでしまう。しかしそこから彼なりに新しい見解を得て再び捜査責任者として再生していく。
彼の転心そのものが禅の「悟り」のパロディなのだろう。脇役の描写にもこんな仕掛けをほどこしているところ、まったく京極夏彦は油断がならない。
本書に収められているのは、なんらかのかたちで「うそ」について書かれたエッセイ−随筆である。なんらかのかたちといっても、私の読んだところでは、大雑把に三つのカテゴリーに分類されるようだ。
まず一つは「うそ」やその周辺の概念(たとえば「パロディ」など)について考察したもの。これに分類されるのは、正直、たいがいがつまらなかった。星新一、筒井康隆、澁澤龍彦、河野多恵子などの名手の手によるものもあるのだが、それでもあまり面白くない。みなさん本業は「うそ」を書くことで、こちらはきわめつきに面白いのに、「うそについて」書くのは得手ではないようだ。逆に彼らの中の「うそ」はあまりにも広く深く、一篇のエッセイに収まるようなものではないのかもしれない。
二つ目はその作品自体が「ウソ」、一篇の「法螺話」になっているもの。これはうまくできていれば見事だが、失敗していたり自分と感覚があわない作者のはちょっと読むのがつらい。前者は別役実の『はなじごく』がさすがにうまい。後者は倉本聰の『巷説・茄子の呪い揚げ』など。
最後は「実世界のうそ」について書かれたもの。といっても身辺の「平気でうそをつく人」や「政治の世界」の話ではない。これらは、私見ではむしろ最初のカテゴリーに属すると思う。そういう浅薄なうそではなく、もっと「芸術性の高いうそ」でなりたっている世界。必然的にアウトロー的色合いが濃くなるが、職人芸と歴史的時間に裏打ちされた世界。たとえば香具師の世界について書いた小沢昭一の『舌耕芸』。俳優である著者の「テキヤ稼業は、私ども芸能稼業の本家のように私は思っておりますから、本家の営業は大事にしたい
」という言葉が著者のプロとしての思いを語って好もしい。話芸そのままのような文章も味がある。
そして本書で一番面白かったのが陳舜臣の『殷周銅器の贋作者たち』。題名通り、台湾の青銅器の偽物(フェイク)の話。地味な題材だが、淡々と偽者造りのエピソードを語りながらラストの短い文章で贋造者の人生を一瞬に浮かび上がらせる。随筆集におさめられてはいるが、短編ミステリーのような切れ味ある一篇。この話自体真偽さだかならぬことが、また面白い。やはり『嘘』というタイトルの書物を読むのなら、騙されるのも快感のうちだ。
 鬼才の書く捕物帳である。江戸情緒の描写にぬかりはないが、まずは第一話冒頭の被害者の描写をお読みいただきたい。
鬼才の書く捕物帳である。江戸情緒の描写にぬかりはないが、まずは第一話冒頭の被害者の描写をお読みいただきたい。
お滝が身につけている粗末な袷は枯草色で、ゆるんだ帯は薄紫の桔梗崩し、乱れた裾からは夕焼け色の蹴出しの裏が覗いている。一枚庭へ倒れた雨戸の向うは、折からの月光の海である。がっくりと首を垂れたうなじの辺りに銀色の漣が打ち寄せ、乱れて傾いた後ろ髷が濡れ濡れと光っているのが怖い。(中略)自らの細い体を委ねた真っ赤な扱帯の余り四尺が、お滝の首から裾の辺りへダラリと流れ、それはまるで名前通りの一筋の赤い滝のようだった。
首吊り死体を描写するのにこの流麗な美文だ。あとはおして知るべし。この水準の文章をうっとりと読み継ぐのはこよなき快楽である。
かといって、捕物帳もミステリーの一分野。謎解き絵解きがおろそかではしらけるが、犯人さがしもちろん暗号解読やアナグラムも出てきてこちらも十分水準以上だろう。最終話では物語全体にかかわる謎が解かれるという構成も王道だ。
なにより陰影や哀感のある人物造形がいい。主人公の半次は幼いときに母を亡くした天涯孤独で「雨上がりの蒼い月と秋の蝶が似合う
」「ちょっとそこらでは見られない美形
」のいい男。手職は絵馬描きだが、腕利きの目明かし「察しの佐助」に育てられ片腕になっている。佐助は御用の途中で腰を痛めて以来足が立たず十手と通り名は一人娘の小夜にあずけて今は推理専門、「居ながらの佐助」と呼ばれている。お小夜ははりきって御用をつとめているが、優しさときっぷのよさはともかく頭脳は人並。父と半次に助けられてばかりいる。そしてもちろん半次にぞっこんだ。
脇役にも気のいい夜鷹のお駒、天才推理小僧のクロベエ。謎の老尼僧花幻尼など、捕物帳にはかかせない魅力的面々がそろっている。
この面子なら、最後でお小夜の恋が成就して大団円というのがお約束だが、作者は久世光彦だからそうはなかなかいくか安心できないところがまたスリリングでいい。優しい半次はお小夜をいつも助け、決してきらいではなさそうだが、夜鷹のお駒の方が気があっていそうだ。実は読者である私もお駒の方が気に入ってしまうのだから困ったものだ。
そんなお小夜のために、彼女が一人歩く美しいシーンを引用して終わりにしよう。
だから、お小夜は、一人で暗闇坂を下りて、日照りの寺町通りを根津の門前町へ向かった。遊郭脇の大銀杏の下を、お小夜の白い日傘がクルクル回っていく。それを追うように、番の紋黄の蝶が、上になったり下になったり、木洩れ日に染まってついてくる。
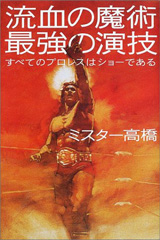 著者は「プロレスに星の売り買いはない」と断言する。
著者は「プロレスに星の売り買いはない」と断言する。
真剣勝負だから売り買いがない、という意味ではない。プロレスは最初から勝負が決まっているショーだから、もとより裏で売り買いする必要などないということである。(中略)
映画のように細かくシナリオが決まっているわけではないが勝ち負けとおおよその流れは決まっている。
そんなことはいまさら読まなくても、少しでも格闘技をやった人や、やらなくともボクシングや柔道の試合をちゃんと見たことがある人なら、とっくにわかっていることだろう。それでも「すべての試合の勝ち負けが決まっている」と、新日本プロレスで二十年以上メインレフェリーを勤めた筋金入りの「業界人」がはっきり断言したことは「プロレス村」にとってはショッキングなできごとだろう。プロレスファンというものは、ほとんどの試合が真剣勝負でない格闘演劇だということがわかっていても、もしかしたら試合の何%かは真剣勝負なのではないか、レスラー個人の強さも勝負にいささかは反映しているのではないか、という淡い期待と幻想にすがって試合を見ているものだからだ。
まあ、そんな幻想は次のような内幕を聞けば木っ端微塵にくだけ散る。
一日の全試合について、マッチメイカーはカード編成と勝ち負けを決める。どこまで細かく指示するかはケース・バイ・ケースだが、この技で決めろ・・・・とフィニッシュまで独断で決めてしまうこともある。その内容をレフェリーに伝え、レフェリーが両サイドの選手に対して、勝ち役、負け役を伝える。
流血のトリック、猪木の生涯ただ2回の真剣勝負、格闘技戦でのボクサー・柔道家とのリハーサル、等々ウラ話は文句なしに面白い。
いわゆる「プロレスラー最強説」なんてものはプロレスラーにとっては有り難迷惑以外のなにものでもないらしい。もちろん強くなければあんな過激なショーはできないのはもちろんだが、だからといって勝ち負けを競う格闘技と同列に論じられてはかなわないということだ。ジャッキー・チェンやシュワルツェネッガーに「映画では無敵だが、タイソンに勝てるか」と聞く奴はいないだろう。
しかし猪木の格闘技戦以降、プロレスラー最強幻想でおいしい思いをした部分もあるのだから自業自得でもあるだろう。猪木によってプロレスがメジャー化したことは間違いないが、馬場プロレスのようなプロレス本来の姿のままでいた方がプロレスにとっては幸せであったのかもしれない。しかしいまさら昔の牧歌的プロレスにもどることもできない。
著者はすべてをカミングアウトしたうえで興行的大成功をおさめているアメリカンプロレス=WWFをプロレスのあるべき姿と規定し、日本のプロレスも似非格闘技からエンターテインメントショーへの脱皮をいそぐべきだと主張する。
まあ、たしかにそのとおりだろうね。その暁には、あの梶原一騎・辻なおきの傑作『タイガーマスク』のような、いささかいかがわしく妖しくてなつかしいわくわくする幻想世界を再現してほしいものだ。
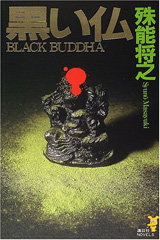 ありゃりゃ、こんどはミステリーとオカルトファンタジー(?)の融合か。ディクスン・カーの『ビロードの悪魔』という偉大な先達があるが、本書は小説構造をミステリーとオカルトの二重構造にしてあるという複雑な構成。
ありゃりゃ、こんどはミステリーとオカルトファンタジー(?)の融合か。ディクスン・カーの『ビロードの悪魔』という偉大な先達があるが、本書は小説構造をミステリーとオカルトの二重構造にしてあるという複雑な構成。
う〜ん、成功しているとはいいがたいなあ。それはひとえにミステリー部分が弱いからですね。オカルト部分もありきたりだし。もう少し分量を増やしてミステリーとオカルトの厚みを増やせば傑作になったかもしれないのに惜しい。小説としてはうまいのでなおさらそう思う。
ということで、本書で殊能将之の現在出版されている著書はすべて読了。私的評価は『ハサミ男』、『鏡の中は日曜日』、『美濃牛』、本書の順。
『ハサミ男』『鏡の中は日曜日』と読み進んできた殊能将之の作品の中では最長の作品。
全編牛のモチーフで被われている。タイトルは、最初の被害者が畜産業で彼が育てていた牛のブランド名なのだが、ミノタウロス伝説も連想させる狙いだろう。
閉鎖的な村に突然、難病を癒す奇跡の泉のうわさがひろがり、取材にきたジャーナリストが、村に伝わるわらべうたを模したような連続殺人にまきこまれる。
俳句をうまく使ったり、あきらかに横溝正史ミステリーを意識した道具立てだ。いかにも本格ミステリー的な味わいが楽しくて読んでいてあまり長さを感じなかった。
殊能作品の中で一番ひねりの少ないまっとうなミステリーと言えるのではないか。推理小説としてのトリックや伏線のはりかた、犯人の意外性は十分水準作。しかし前作(『鏡の中・・』は書かれたのはあとだが)で立て続けに見事にだまされた快感が忘れられない身としては、少々ものたりない。
新人にしては刑事や登場人物の造型はいつもながらしっかりしていてうまいなと思う。このへんがだめなのは、いくらトリックなどがすごくても読む気がしない。その点、この著者は比較的安心して読める。
ということで同じ作者の『黒い仏』を続けて読んでいる。同じ傾向の本を続けて読めない私にしては珍しい。
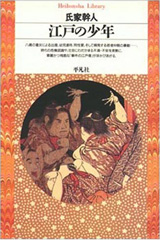 時代劇やチャンバラが好きだ。タイムマシンが懸賞であたったら、行ってみたいのは一にジュラ紀(もちろん恐竜を見るのだ)、二に江戸時代だ。
時代劇やチャンバラが好きだ。タイムマシンが懸賞であたったら、行ってみたいのは一にジュラ紀(もちろん恐竜を見るのだ)、二に江戸時代だ。
もちろん、時代劇の描く江戸時代がうそっぱちなのは先刻承知。小説だって、もしかしたらノンフィクションだって「江戸時代の理想化」というウソの点では五十歩百歩かもしれない。だからこそ江戸の実相を少しでも知りたくてこんな本を読むのだが、『大江戸死体考』で「死体だらけの江戸」を書いた著者が今回焦点をあてるのは、江戸時代の少年少女=若者たちのありようだ。
のっけから「八才の童女が妊娠して出産した」というスキャンダラスな事件の紹介から本書ははじまる。現代ならネットやワイドショーや女性週刊誌が大喜びするところだが、江戸時代(事件は文化九年)でもかわら版が出るほどの大騒ぎになったそうだ。見物に来る人が多すぎて百文の見物料をとったという話まで伝わっているようだ。面白いのは地元領主の対応だ。時代劇などの印象からすると、「不吉な」とか「不埒な」なんていって親子を罰しそうな気がするが、事実(を調べるのも大変なのだけど)は全然違うようだ。
代官手代が親子を直接調査した注進書を上申し、幼い母子は殿様の御前に伺候したという。ねぎらいの言葉をかけられ三人扶持をたまわったらしい。支配する側としては人心の動揺が一番困る。とりあえず「めでたいこと」としてしまうのが無難だということだろうか。
「楽園の中で」の章では、明治時代に日本にきた西洋人が共通してもったらしい日本の印象「子供の天国」がほんとうだったのかを検証する。最近の児童虐待なんてかわいいもんだと思うような事例がたくさん。
「遊びと反乱」「若者たちの領分」「制度としての逸脱」の章では、「反抗する若者」としての江戸の少年たちの姿が描かれる。長幼の序が絶対で、現代よりずっと親の子への支配力は強固だと思われていた江戸の世が、意外とそうでない局面があったことを、著者は古文書や歌舞伎や祭りの習俗などの資料を駆使して指摘する。
しかし、なんといっても目からウロコなのは「アナザー・カントリー」の章だ。「やおい」などは裸足で逃げ出す「男色」の話なのだが、どうも現代のわれわれが同性愛や男色に持つイメージと江戸のそれはだいぶ違うようだ。「いまでこそ同性愛も社会的に認知され」などというフレーズがいかに間違っていることか、江戸時代では認知どころか「あたりまえ」のことだったらしい。どのくらいあたりまえかは、本書を読んでいただくこととして、それ以外にも私がいつのまにやら身につけていた「江戸時代の常識」に反する事例がたくさん載っている。
あとがきで著者は書いている。
読者が抱いていた江戸時代の少年世界観になんらかの修正と補足を加えることができたならば、せめてもの救いである。
だいぶ修正されました。
「21世紀本格」 島田荘司編/瀬名秀明他 (カッパノベルス)
 本書の白眉は収録された作品よりもむしろ、編者島田荘司による巻頭の「序文に変えて」だろう。
本書の白眉は収録された作品よりもむしろ、編者島田荘司による巻頭の「序文に変えて」だろう。
探偵小説というジャンルは、1841年のエドガー・アラン・ポーの『モルグ街の殺人』に端を発した。その後「探偵小説」は「ミステリー」として、多彩なサブジャンルへと進化発展したわけだが、島田荘司は
この歴史的傑作の「核」は何処にあったかというと(中略)神秘的な幽霊現象と、時代の最先端の科学とを出逢わせた「精神」にあった
と考える。科学は20世紀に入っても休むことなく前進を続けた。
しかし、本格よりのミステリーは、自身の安定発展のために、いわばこの事実を無視し、逃避することで別個に成長を遂げていきました。科学の最新成果に都度接近する勇気は、SFジャンルの才能に任せたわけです。
島田はしかしそれをよしとせず
もしモルグ街の殺人を今一度引き起こし、このジャンルの小説世界を新たにスタートさせることを試みたなら、現れたモルグ街の現場ははたしてどのような様相を呈するものか
と新進気鋭のミステリー作家に「執筆依頼状」という形でアジをとばす。島田の呼びかけに答えて書き下ろされた七編に編者自身の「見本作品」を加えたアンソロジーが本書である。
その意気やよし。さすがに収録作品は勘違い?と思わせるものもふくめすべて力作ではある。ただし、本格、SFどちらかの色が濃い作品に別れ、これが新時代の本格だ、という正解はなかったようだ。
以下、収録順に感想を。
響堂新「神の手」。H.G.ウエルズの『モロー博士』とホームズものの『まだらの紐』の合わせ技。医系の作家だけにクローン技術をそつなくネタにしてるのだが、新鮮味はない。ミステリとしての意外性はまずまずだが、「21世紀」作品としてはこのラストから物語を進ませねばだめでしょう。たとえ短編だとしても、読者に未来を暗示させるような方法はあったはずだ。
島田荘司「ヘルター・スケルター」。みずから「見本」としただけにさすがにうまい。小説としては一番面白い。「故障した脳」という最先端のモチーフをもとにトリッキーなミステリーに仕立て上げている。収録作中一番科学とミステリーのバランスがとれていて、文章もうまい。しかし爆発力という点ではどうか?
瀬名秀明「メンツェルのチェスプレイヤー」。爆発力衝撃力ではこちらが上か。タイトルからしてポーの名作から取っている力作。テーマは人工知能だが、トルコ人の衣装をつけたロボットが無気味だ。自分を生みだした科学者を惨殺した(らしい)ロボットとチェスの勝負をしなければならなくなったヒロイン(諸星大二郎の『碁娘伝』を連想してしまった)。負ければチェスプレイヤーのクローンロボットが豪華客船で虐殺を開始する。はたしてロボットの動機はなにか?一番「21世紀本格」を感じさせる作品。このくらい専門知識がないとこれからの本格は難しいのだろう。『パラサイト・イブ』を読んで以来、この作者は敬遠していたのだが、見直しました。
柄刀一「百匹めの猿」。ある自然現象が同時に関係ない場所で自然発生する共時現象=シンクロシニティによる殺人と見せて実は・・・・という内容だが、「実は」の真相の方もなんだか説得力にかける。私には一番つまらなかった。今感想を書くのに内容が思い出せずに困ったくらいだ。
氷川透「AUジョー」。狂牛病のために人口が激減した近未来の日本。治安のため居住区は細分化され「関所」が設けられている。・・設定は魅力的だ。「神の手」と違い科学的事実からちゃんと未来を演繹して異世界を構築してる点は好感を持てる。この江戸時代のような社会に殺人が起こる。犯人はいるはずのない人間だった・・。ミステリーとしてもなかなかだと思う。しかしこれだけ今と違う社会なのに、登場人物のメンタリティが現代人と変わらなく思えるのは、SF的視点からはちと物足りない。
松尾詩朗「原子を裁く核酸」。わけのわからないタイトルだが、内容もトンデモもたぐい。テーマはまあダイイング・メッセージだが、「どんなバカでも、こんなことしないでしょ?!」と小一時間問い詰めたくなることは必定。いわゆる新本格の一番悪い面が出たというとこでしょうか。この面子にまざるには、少々家賃が高かったか。
麻耶雄嵩「交換殺人」。「科学との融合」という本アンソロジーのテーマを見事なまでに無視して、「ミステリのサブジャンルの極北」を目指した作品。幾重にも入り組みどんでん返しが見事な「交換殺人」テーマとしては申し分ない。しかし「こんな複雑なことするより、ポンと殺してすっとぼけてたほうがましなのでは」と思ってしまう私は、本格ミステリにはもともとむいていないのかもしれない。だからこそ、そこを納得させてくれる作品を読ませてくれれば、一も二もなく降参してしまうのだがね。
森博嗣「トロイの木馬」。こちらは本格的なSF。仕事もプライベートな生活もヴァーチャルな空間で行うことが普通になった未来。そんな世界での愛や陰謀を描いて間然とするところのない傑作。主人公はオンラインでの謎をさぐるためオフラインで行動し現実と虚構の迷路をたどっていくのだが、結末で明らかになる真相は、まるでイーガンのようだ。SF的意味でのミステリー要素は完璧だが、本格ミステリかといわれれば自信を持って違うといえる。
こうしてみると、どうも私の感想は本格ミステリ寄りの作品よりSF寄りの作品に点が高いようだ。これは単に私の嗜好の問題なのか、本格ミステリーというジャンルそのものが「21世紀」的ではないからなのか。単純にそのときの個々のできの違いによる偶然か。どれなのだろう。
 もし、自分のお気に入りSFベストをあげるとすれば、バラードは絶対外せない作家だ。私が昔SFに耽溺しはじめた頃は、バラードには「あたらしい波」の作家として難解なイメージがあった。そのためしばらくは敬遠していたのだが、のちに読んだ短編『ヴァーミリオン・サンズ』シリーズで、そのめくるめくイメージの氾濫に心臓をつかまれて久しい。長編『夢幻会社』や『奇跡の大河』は、私の読んだすべての小説の中でも常にトップ10の位置を占めている。
もし、自分のお気に入りSFベストをあげるとすれば、バラードは絶対外せない作家だ。私が昔SFに耽溺しはじめた頃は、バラードには「あたらしい波」の作家として難解なイメージがあった。そのためしばらくは敬遠していたのだが、のちに読んだ短編『ヴァーミリオン・サンズ』シリーズで、そのめくるめくイメージの氾濫に心臓をつかまれて久しい。長編『夢幻会社』や『奇跡の大河』は、私の読んだすべての小説の中でも常にトップ10の位置を占めている。
著者が1996年に上梓した本書はSFではない。
まるで『サイコ』のスタイルでリメイクされたカフカではないか」
というのが帯の惹句なのだが、これだけではなんだかわからない。
主人公は旅行作家。放火殺人罪に問われた弟の嫌疑をはらすべく、スペインの架空の避暑地「エストレージャ・デ・マル」を訪れる。弟を知る住民たちは全員弟がやったはずはないといい、弟は罪を認めて詳しいことは話さない。不可解な事態に主人公は調査を続けるが、やがて街そのものとその住民の迷宮のような不可解さに迷いこみ、街で多発する犯罪の黒幕らしき不思議な若者に魅了されていく・・・・
物語はミステリの体裁をとり、謎が次々と提示されストーリー展開はサスペンスフルで、犯人も弟の動機もはぐらかされることなくあかされる。
しかし本書の謎は放火殺人の犯人ではなく、街そのものの不可解さの方だ。白く魅惑的なリゾート地。周辺地域の住民は衛星TVを呆然と見るだけの倦怠の日々をおくっているというのに、エストレージャ・デ・マルの人々はいきいきとスポーツや趣味を積極的に楽しみ、多発する事故や犯罪を苦にするようすもない。なぜだ?
本書で著者が書いた「エストレージャ・デ・マル」は、ヨーロッパの、ひいては世界の未来の姿なのだろう。その意味では「SFではない」というのは見当違いで、本書は広義のSF、未来小説としてのSFといえるだろう。
なにはともあれ小説としてステージが高いのはまちがいない。いわゆるハリウッド的面白さとは違うが、ハードカバー二段組み350頁を一気に読まされてしまった。練達の文章(訳もうまいのだろうね)で描きだされるリゾート地が魅惑的だ。陽光にあふれ美しく退廃していて活気にあふれ、犯罪が多発してるが善意がいっぱい。
細部、たとえば海岸のゴミまで描写するリアリティは、初期の『結晶世界』や『沈んだ世界』の破滅した世界のリアルさを思い出させられてなつかしい。
やはりバラードは永遠のニューウェイブであるね。
 パスティーシュの名手として名高い著者の、数ある短編の中で私が一番好きなのは『国語入試問題必勝法』だ。正解というものがあるのか大いに疑問である文芸や文学に正解を求める、ある意味強引といってもいい「国語」という教科の構造そのものをパロディにした、再読に耐える(何回も笑える)傑作だ。
パスティーシュの名手として名高い著者の、数ある短編の中で私が一番好きなのは『国語入試問題必勝法』だ。正解というものがあるのか大いに疑問である文芸や文学に正解を求める、ある意味強引といってもいい「国語」という教科の構造そのものをパロディにした、再読に耐える(何回も笑える)傑作だ。
著者には小説以外にも『もっとおもしろくても理科』、『 清水義範の作文教室 』など「教育ネタ」の秀作がたくさんある。さすがは名古屋教育大卒だ。その著者が満を持して(と私には思えた)放った教育ネタ長編奇想風刺小説が本書だ。
のんびりと執筆生活を送っていた(著者の分身)とも思える小説家が、謎めいた地元中学校に妻子を拉致され、心ならずも戦いを挑んで行く。彼の前に次々と現れるエキセントリックな教師は、いずれも自分の教科に異常なまでに誇りを持ち、教育を風刺する小説を書く主人公に敵意と反感を持っている。
まずは教師たちは作家が世間で「先生」と呼ばれるのが気にいらない、というのが笑ってしまう。先生と呼ばれていいのは自分たちだけだというわけだ。申し訳ないが、なんだかほんとうにそう思っている「先生」がいそうな気がしてしまうではないか。
前半の教師たちと主人公が交える各教科ごとのバトルが圧巻である。まさに著者自身があとがきで書いている「教育テーマのエンターテインメント小説
」だ。
これが後半、SF調な展開になってくるとややだれる。やはり本書の真骨頂は「ギロンによるチャンバラ小説
」(これもあとがきより)の部分だろう。
登場する教師たちのネーミングがいい。社会科教諭は与野惑成、国語科主任は五車卓一(。なんとなくわかるでしょ。ではもうひとりの国語教師の清野愛児(という命名は、なんのパロディなのでしょう。知りたい方はぜひ本書を。笑えます。
著者の友人には教師になっている人が多いという。ここまで書いてしまって、友人たちとの仲はだいじょうぶなのだろうか?
 掲示板で「速読」の話が出たが、それと対極にある「音読」の本である。
掲示板で「速読」の話が出たが、それと対極にある「音読」の本である。
現代の読書の主流は「黙読」だろう。しかしそれは近代小説以降のことで、もともと聖書などは聖職者が民衆に向かって朗唱して聞かすものだったそうだ。それがグーテンベルグの聖書印刷によって個人の手にわたり北ヨーロッパの冬ごもりの生活の中で「黙読」の習慣が生まれた。そこからイメージを(語り言葉でなく)書かれた文字で操作する近代小説へとつながっていった、という説がある。
その反面、黙読を基礎におく近代文明の前で「朗誦・暗誦文化」が衰退していっっているのはたしかだろう。コーランを朗誦・暗誦することを絶対とするイスラム文化が反近代の様相を帯びるのもむべなるかな。
日本にも漢詩や芝居の科白を暗誦して「楽しむ」文化は、つい最近までたしかにあったはずだ。しかし現代の大学生で暗誦できる好きな詩や文章を持っている者は5%以下だそうだ。本書は日本の生活に根ざし(てい)た「朗誦・暗誦文化」の復権を目指したものだ。
小難しい理屈はともかく、内容は暗誦しやすく声に出して楽しいテキスト集だ。本書を読むのに黙読は厳禁。なにはともあれ声を出さねばはじまらない。学校でやらされたときはイヤだった音読が、自分からやってみるとこんなに爽快だとは思わなかった。家族にはうるさがられたけどね。
収録されているのは教科書でおなじみの「平家物語」「万葉集」「奥の細道」などのさわりから、浪曲「森の石松」、新国劇「国定忠次」といった大衆文芸、落語の「寿限無」、大道芸「ガマの油」まで多岐にわたり種々雑多だ。
なかでも一番リズミカルでただただ気持ちがいいのは、やはり歌舞伎の名科白だ。以下に引用してみる。できればIEでルビをオンにしてみてもらいたい。
河竹黙阿弥(『弁天娘女男白波((白波五人男()』より
知らざあ言って聞かせやしょう。浜の真砂(と五右衛門が、歌に残せし盗人(の、種はつきねえ七里ヶ浜、その白波の夜働(き、以前をいやあ江ノ島で、年季勤めの児ヶ淵(。百味講(でちらす蒔銭(を、当てに小皿の一文子(、百が二百と賽銭(の、くすね銭せえだんだんに、悪事はのぼる上の宮、岩本院(で講中(の、枕探しもたび重なり、お手長講(の札つきに、とうとう島を追い出され、それから若衆(の美人局(、ここやかしこの寺島で、小耳に聞いた音羽屋の、似ぬ声色(で小ゆすりたかり、名さえ由縁(の、弁天小僧菊之助(たァ、おれがことだ。
なにか漢詩の一つも覚えて夜道を朗誦しながら帰るとするか。ちょっと前までなら変な人だが、最近は携帯電話で話しながら歩いている人も多いので、耳に手をあてながらならだいじょうぶそう。か?
これもシリーズ一作目を読まずに二作目から読んでしまったので、主人公のシャルルには初対面。
シャルル・ドゥ・アルディ、弱冠二十三歳にして医学博士。パリ在住の鑑定医にして天才心理学者。白金の長髪、青灰色の瞳、超然とした美貌、冷ややかな無表情、聡明な理性。他人を博士論文を書くための研究対象としかみない超然とした(歪んだ)性格。・・・・なんだか少女マンガによく出てくる美形のおにーさまを想像してしまった。実はかすかに優しい面もありそう、なんてとこまでマンガの主人公っぽい。
話は例によって深層心理をフロイト理論でさぐる精神分析ミステリ。意外な犯人もさほど意外ではないが、事件の解決によって家族が再生に向かうシーンは結構感動させられてしまった。どうも、この著者のストーリー運び、抜群にうまいわけでもないのだが、私の好みには合っているらしい。
『侯爵サド夫人』でもそうだったが、友情というか、男同士の関係を書くのもうまい。シャルルの才能をかって、彼といい関係をもとうとする、やりての巡査部長デュロンの造形がいい。部下とシャルルの間にはさまれて、どちらの顔もたてて自分の保身にも気をくばり捜査をスムーズに運ぶてぎわは、公務員の鏡といえましょう。世故にたけてはいるが、仕事上で少女娼婦にせまられても据え膳を食ったりはしないところは、どこかの国の不祥事続きのどこやらは見習うように。
 著者の実質的デビュー作『ハサミ男』でまんまとだまされたというのに、またもだまされてしまいました。
著者の実質的デビュー作『ハサミ男』でまんまとだまされたというのに、またもだまされてしまいました。
見事なトリックなのに、本書はミステリのお約束を批判するアンチミステリでもあるところが面白い。『名探偵の掟』のような「パロディ」ではない。小説の構造そのものが、いわゆる本格探偵小説への批判(がおおげさなら、からかいか?)になっているのだ。
痴呆症の老人の一人称、という怪しげな形式の第一章からはじまるのだが、私は読了後、この第一章を何度も読み返すはめになった。と書いても絶対ネタばれにはならないのでご安心。
第二章でやっとシリーズの名探偵石動戯作が登場する。といっても私は前作の『黒い仏』も前々作の『美濃牛』も読んでないので、彼とは初対面だ。
今回持ち込まれたのは、十四年前(石動がファンの)名探偵が既に解決済みの事件の再調査だ。ここから過去の事件の顛末と現在の探偵の調査が交互に描かれていく。過去の事件は出版元の内容紹介を引用すればこうだ。
鎌倉に建つ梵貝荘は法螺(ほら)貝を意味する歪な館。主は魔王と呼ばれる異端の仏文学者。一家の死が刻印された不穏な舞台で、深夜に招待客の弁護士が刺殺され、現場となった異形の階段には1万円札がばらまかれていた。眩暈と浮遊感に溢れ周到な仕掛けに満ちた世界に、あの名探偵が挑む。隙なく完璧な本格ミステリ!
しかしこのきらびやかな、いかにも新本格的テイストに満ちた怪事件が、十四年後に再調査する探偵の目には少し違った様相を見せてくれる。文学や恋愛談義にふけっていた登場人物たちは老け込み、棺のような印象だった館「梵貝荘」は平凡な家屋にしか見えない。時が変貌させたともいえるけど、元々現実はこうだったのじゃないの、という作者のつぶやきが聞こえるようだ。
宮部みゆきが『模倣犯』で「事件の行間」を書いたとすれば、殊能将之は本書で「事件の解決のその後」を書いたといえるだろう。ここでいう、事件の解決とは新本格で名探偵が登場人物を一室に集めて謎解きをやる、あの「解決」ですね。
そういう批判的な構造を持ちながら、本書のトリックは本格ミステリとして十分に面白い。皮肉にも、いささか偶然がすぎるという本格ものの弱点を感じるものの、まあミステリの許容範囲でしょう。
私自身は第三章のどんでん返しより、過去と現在が違う容貌を見せる第二章の方が面白かった。いや、見事にだまされたくやしまぎれではないよ。
ラストはちょっと心温まるエピソードで、読後感は悪くない。
 本書で紹介される画家は、たとえばデルヴォー、マグリット、ベルメエル、レオノール・フィニイ、バルチュス、ベックリン、エルンスト、ゾンネンシュターン、エッシャー・・・・たまらない面々だ。
本書で紹介される画家は、たとえばデルヴォー、マグリット、ベルメエル、レオノール・フィニイ、バルチュス、ベックリン、エルンスト、ゾンネンシュターン、エッシャー・・・・たまらない面々だ。
いま聞くと、好きな絵にルノワールやセザンヌをあげるより、ちょっとインテリ(死語?)っぽいかなというラインナップ。しかし本書の単行本が初版刊行されたのは1967年、日本ではいずれの画家も決してポピュラーではなかった時代だ。彼らの知名度が日本で上がっていったのは、澁澤龍彦のおかげである、といってさほどまちがいではあるまい。
そしてこれは澁澤龍彦の他の著作にもいえることだが、衒学趣味の人にありがちな難解な文章は絶対あらわれない。平易な文章で高度な思想が語られる。きっとスタイリッシュな澁澤先生にとっては難解な文章ほどみっともなくかっこわるいものはなかったのだろう。
巻末近くにおさめられた、「人形愛」「玩具考」「仮面のファンタジア」といった、作家論をはなれた小文たちが意外と楽しい。
「煙草屋の密室」 ピーター・ラヴゼイ (中村保男訳/早川ミステリ文庫)
友人知己お薦めのミステリ短編集。
ミステリといっても純然たる謎解きはほとんどない。ひねりのきいたオチが楽しめる「粒ぞろい」の作品集だ。いずれも分量が文庫版で20頁から30頁と揃っているのも、著者の職人芸が感じられて読みやすい。
表題作が色々なアンソロジーにもおさめられているほど有名だが、私のお気に入りは巻頭の『肉屋』。さりげないでだし。事件がたちあらわれるじわっとしたサスペンス。逆転のおち、ほのぼのさせる結末。巧緻きわまりない逸品だ。『秘密の恋人』も「いやらしくない艶笑譚」で私好み。
『ヴァンダル族』も短いながらオチがちょっとショッキングで心に残っている。表題作の「煙草屋の密室」と同じ種類のネタだが、著者にはなにかトラウマになるようなことがあったのだろうか。(ネタばれになるので、はっきり書けないのがもどかしい)
語り口といいストーリー展開といい、翻訳物のこの分野の現代作家では最高水準でしょう。私が読んだ中で比肩しうるのはジェフリー・アーチャーくらいか。
よくできたホラーサスペンス。もちろんレイモンだからスプラッタ描写もそこそこあるがたいしたことはない。
今回の怪物は人間の体内にもぐりこみ、首筋に居座って宿主を支配するというハインラインの『人形つかい』系の蛇状の生物。乗っ取られた人間は怪物から送られる快感にあやつられ、殺人をくりかえし犠牲者をむさぼり脳髄をすする。ただ、食性は変るが別に超人的能力を得られたりはしないので、怪物というよりやはりサイコキラーのようだ。
舞台になるのは邦題のとおり大学のキャンパスなので、犠牲者になるアメリカの女子大生の日常がじっくり書込まれる。ヒロインの恋の悩みがかなりの分量を占め、ホラーとしてはややバランスが悪い。その分、登場人物に感情移入できるのでラストのサスペンスは盛り上がるけどね。
評価:『殺戮の野獣館』には及ばないが『逆襲の野獣館』よりは面白い。
 もちろん『チャタレイ夫人の恋人』の作者D.H.ロレンスの短編集。
もちろん『チャタレイ夫人の恋人』の作者D.H.ロレンスの短編集。
性の探求者とか自然の礼賛者とか、いろいろ言われている著者の特色は短編にも色濃く現れている。まあ、そんなことより私がロレンスの短編を読むときのたのしみは『乾し草小屋の恋』でも書いた無垢な男と女の緊迫した対峙
だ。
例えば「博労(の娘」。父の死によって破産し離散を目の前にしている一家。兄たちは無力感から自棄的になっていた。ただ一人誇りをたもっていた娘メイベルも生きる支えを失おうとしている。その一家を気にかけている若い医師ファーガソンは献身的な働きをしながらもなじめぬ地域と思うようにいかない日常に苛立ち疲れ切っていた。ある日、彼はメイベルが夢遊病のように池に身を沈めたのを発見、救出する。蘇生した娘は医師が彼女の衣服を脱がせ救命したことを知り、「わたしを愛してくださってるのね?」とささやく。突然の告白に医師は困惑するが、娘はうわごとのように愛の言葉をささやき続ける。医師は動転し当惑し、反発さえする。しかし、おしとどめようとした彼の手が彼女のむきだした肩に触れた瞬間、全てが変っていく・・・・
別に二人はセックスするわけではない。しかし会話と独白でつづられていく心理の変化の緊張感あふれる描写は、ヘタな性愛描写より官能的だ。
「白い靴下」はコケティッシュな妻との夫のいさかい。
「盲目の男」では盲目の夫と、彼の妻が呼んだかつて彼女に求愛していた友人のぎこちない対話。
いづれも二人の人物の緊張した人間関係と心理のダイナミックな変化が、会話だけで描写される。
他にドンファン的色男が女たちに復讐されるコミカルな「乗車券を拝見」なんてのも面白いが、やはりロレンスの真骨頂は上記のような緊張感が支配する小説だと思うし、私は好きだ。
「逆襲の野獣館」 リチャード・レイモン (大森望訳/扶桑社ミステリ文庫)
 もちろん、あの掟破りのラストでホラーサスペンス読者の度肝をぬいた怪作『殺戮の野獣館』の続編。
もちろん、あの掟破りのラストでホラーサスペンス読者の度肝をぬいた怪作『殺戮の野獣館』の続編。
今回の人間側の悪役、ホラー作家ゴーマンのキャラクターがなかなか楽しめる。前作の幼児姦犯ロイのようないかにもな反社会的人間ではない分、成功のために手段を選ばない鬼畜ぶりが妙にリアルだ。
しかし、あとはちょっと・・・・
前作の倍近い分量で、呼び物のセックスとバイオレンスの描写もたっぷりだけど、残念ながら雰囲気も衝撃度も前作にはとても及ばない。ちょっとくどいクーンツという感じで、普通のホラーサスペンスになってしまっている。その限りでは十分楽しめるけどね。
う〜ん、「野獣」の正体もラストも平凡だ。
次に読む予定の『殺戮のキャンパス』は一作目のような鬼畜度だといいなあ<もしもし
<前 | 日付順目次 | 書名索引 | 著者名索引 | 偏愛選書 | 次>