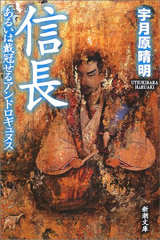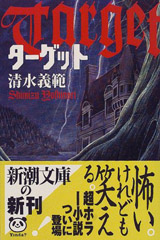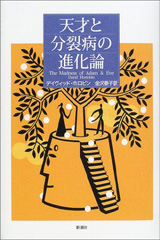◆ 歯皮膚屁本 - はひふへほん ◆ HOME
<前 | 日付順目次 | 書名索引 | 著者名索引 | 偏愛選書 | 次>
読書日記 2003/01-06
 副題が「カルト本の百年」
副題が「カルト本の百年」
「偽史」=日本史上の珍説奇説で一番有名なのは、やはり「義経は衣川で死なずに大陸に渡りジンギスカンとなった」説だろう。漱石の『吾輩は猫である』にも出てくるエピソードだ。判官贔屓=歴史上の悲劇の英雄への同情が生んだ幻想であり、世界史上の大英雄が実は日本人だったという自己愛肥大妄想でもあるだろう。しかし、この奇説が大正デモクラシーの時代に出版され、当時の日本人から熱狂的に迎えられてベストセラーになったと聞くと、ちょっとおだやかではない。
この奇説を著わしたのは小谷部全一郎。いわゆる奇人変人ではない。歴史学者ではないが陸軍通訳官であり大学で教鞭をとっていたこともある。その彼の『成吉思汗ハ源義経也』は一般庶民だけででなく、華族会の後押しをうけて一種の権威を持つようになった。
アジアのほぼ全域を手中に収め、ヨーロッパまでも脅かしたジンギスカンが実は日本人であるということは、小谷部の心のなかでは、そのまま自己の偉大さ、日本人の偉大さの証明であった。
それだけでなく、義経=ジンギスカンの支配により「大陸の人々には日本人の血が流れており
」ジンギスカンと同じ騎馬民族によって創始された清国は清和源氏という皇族の末裔ということになる。すなわち、のちの「アジアはみな家族兄弟、優秀な長男である日本の指導のもと欧米の支配を打ち破る
」大東亜共栄圏思想に正当性を与える物語だったのである。
もちろん本書で紹介されるのは義経伝説だけではない。「日本=ムー大陸説」「トンデモ日本人起源説」「日本ユダヤ同祖説」「漢字渡来以前に日本独自の文字があった神代文字説」。いずれも日本と日本人の偉大さを証明しアジア侵略の正当性を側面から補完する説として、当時の日本軍部などからはかなり歓迎されたらしい。
しかし、わが国は他のアジア人より優秀だから支配して当然、というような欧米的な単純な動機ではなかったようだ。「日本ユダヤ同祖説」を唱えた日本人はキリスト教徒だったが、アメリカでひどい人種差別にあい、「キリスト教徒である白人が差別主義者になってしまったのはユダヤ人の陰謀であり、日本人こそが正しいユダヤ人である」という、かなり屈折した発想から同説を唱えるにいたったようだ。
白人への反感から日本主義に凝り固まりながら、かれらと同じようにユダヤ人を差別することで彼らと同じ側に立ちたいというアンビヴァレントな思いを抱いていた
妄説といっても、すべからく時代精神と結びついていて一筋縄でいかないということだが、現代のわれわれも妄説から自由になっていないことは、2ちゃんねるあたりをのぞくとあきらかである。できるだけ、自分も自分の国も誇大視することなく卑下することもなく等身大で見たいものである。
といっても、われらが日本だけでなく、お隣の国やその向こうの国や太平洋の向こうのでかい国や、どこもかしこもみんな、自分自身を等身大で見てるとこなどありそうもないなあ。
 こちらは時代小説、歴史小説の種本として有名な『武功夜話』の研究書。旧くは遠藤周作近くは堺屋太一、津本陽といった作家が著作の材料とし、第一級の史料として持ち上げている。堺屋原作のNHK大河ドラマ『秀吉』のエピソードはほぼこの『武功夜話』におっている。
こちらは時代小説、歴史小説の種本として有名な『武功夜話』の研究書。旧くは遠藤周作近くは堺屋太一、津本陽といった作家が著作の材料とし、第一級の史料として持ち上げている。堺屋原作のNHK大河ドラマ『秀吉』のエピソードはほぼこの『武功夜話』におっている。
この「歴史書」はもともと愛知県江南市の吉田龍雲家という旧家に同家の先祖である前野一族から伝わった書き物の一つだというのだが、世にあらわれたのはそんなに遠い昔ではない。昭和34年(1959年)に伊勢湾台風で崩れた吉田家の土蔵から現われたという劇的な「発見」のされかたをしている。
しかしこの『前野家文書』が有名になったのは、直接一般に公開されたり公的機関で研究されたりしたからではない。吉田家当主の弟という人物が「全訳」したものが新人物往来社から1987年に『武功夜話』として出版された。その本が前述のとおりマスコミや有名作家にとりあげられはじめて評判になった。いまも歴史学者の中に一級史料として高く評価する人も少なからずいるらしい。
残念ながら、私は実物を読んだことはないが、戦国史は好きなので『武功夜話』の名前は知っていた。著者であるとされている前野氏は織田家につかえていたので、同書に登場するのは信長、秀吉、信長夫人、蜂須賀小六、千利休、石田三成、細川ガラシャなど戦国史の大スターたちだ。桶狭間合戦などの有名なエピソードも詳細に記述されているらしいし、面白くなかろうはずがない。
しかし、本書の著者である二人の戦国史研究者は『武功夜話』の信憑性に疑念を持ち、読込んだ末に偽書であると結論づける。
その論証の中身は実に面白い。詳しいことは本書を読んでいただきたいが、書かれたエピソードの相互矛盾などは勘違いということもあろうが、戦国時代の価値観や常識からかけはなれた記述が頻出するというのが面白い。
たとえば弓兵隊を指す「弓手衆」という言葉が出てくるが、これは戦国時代はおろか江戸時代でもこんな言葉は使われていないという。「弓衆」または「弓足軽」であって「弓手」は左手のことだ。つまり『武功夜話』は戦国時代どころか江戸時代の偽書でさえなく、劇的に「発見」された直前、昭和に書かれた疑いが濃厚ということなのだ。なぜこのようなことが行われたか、本書の著者たちは「犯人」の心理の推理はするがあえて非を責めたてようとはしていない。
その情熱というか執念は、まことに驚くべきものであるが、ことさらに世間を騒がせようとか、学会を混乱させようとかいう意図があったわけでもあるまいから、その人を責めても仕方がないだろう。むしろ、市井の日本人の「歴史意識」についての一つの研究素材と考えれば足りることかもしれない。問題としなければならないのは、無批判にそんなもののチョウチン持ちをし、すばらしい史料であるかのような情報を日本中に垂れ流す役割を果たした一部の学者、文化人、マスコミ関係者などの存在であろう。
なんだか『武功夜話』を無性に読みたくなってきてしまったぞ。
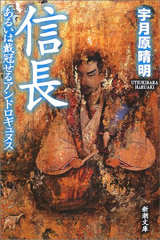 こちらは史実もへったくれもない、なにしろあの織田信長が両性具有のフリークスで秀吉も光秀も信長の激しく厳しい戦いについていったのは、彼(彼女?)の「魅力」のとりこになっていた、というのだから奇想も極まれり。
こちらは史実もへったくれもない、なにしろあの織田信長が両性具有のフリークスで秀吉も光秀も信長の激しく厳しい戦いについていったのは、彼(彼女?)の「魅力」のとりこになっていた、というのだから奇想も極まれり。
たしかにあの美男の肖像画や妹のお市の方が絶世の美人であったということを考えれば、そんな妄想もすこしはありかなとも思うが、しかしねえ。
そんな奇天烈な設定でいながらストーリーを史実と矛盾させず、歴史上の信長の謎を妙にしっくり解釈させる著者の筆力はたいしたものだ。幻想伝奇戦国小説として十分に成功している。信長のあらわな乳房のシーンだけで読む価値あり(なのは私だけか?)
ナチが台頭する時代のドイツと日本の戦国時代を交互に舞台にして、ローマ皇帝までを関連づける趣向は最初はうるさく感じたが、ラストではなかなか効果的に決まっている。
ローマ皇帝ヘリオバルガス → 織田信長 → ?
 短編集。篠田節子ははじめて読んだけど、面白い。皮肉さと冷たさと暖かさがちょうど私好みの塩梅だ。
短編集。篠田節子ははじめて読んだけど、面白い。皮肉さと冷たさと暖かさがちょうど私好みの塩梅だ。
「幻の穀物危機」 現代日本に食糧危機が来て社会秩序がくずれたとき、誰が一番強いのかという話し。生産手段を持つ農民か。車を武器に略奪集団と化した都会人か。なんといっても都会から脱サラして農村でパン屋を営んでいた主人公が一番立場が弱かった……
「やどかり」 児童相談所で研修中のエリート青年が不登校の女子中学生にふと出した親切心が思いもかけぬ事態に……。陥穽の描き方がリアルで自然。
「操作手」 老いをテーマにしたSF?ひさうちみちおの『おじいちゃんがやって来る』という短編を思い出してしまった。秀作。
「春の便り」 ホラーショートショート。犬好きな人は涙をさそわれるにちがいない。
「家鳴り」 正統派心理ホラー。理想的なしかしセックスレスの若夫婦に訪れる恐怖。途中までの展開はなかなか読ませるが後半は予想がついて意外性に欠けた。
「水球」 バブリーな時代にうかれすぎた典型的なサラリーマンの末路を描いた、ホラーでない普通の小説。ラストの絶望感に対峙する水球(卓上球形水槽)のあつかいが秀逸。
「青らむ空のうつろの中に」 母親に虐待され口を聞かなくなった少年が「施設」の農場に預けられる。不適応児童が「人間らしく生きられる」施設の描写は実在の「ヤマギシズム」などを連想させる。もちろん理想郷などあるはずもなく、少年は施設でも心を開かず、ただ豚舎の雌豚にのみ親しみを示す。そんな彼がある日事件を起こす……
いずれも力強く読みごたえのある短編。ただし作風は人によって好ききらいはありそうだ。
 『家鳴り』を読んだときも、児童相談所やそこに相談に来る人の描写がえらくうまいなと思っていたが、著者の「市役所の福祉事務所に勤務」という経歴を知って納得した。本書はその福祉事務所のケースワーカーを主人公にした連作集。
『家鳴り』を読んだときも、児童相談所やそこに相談に来る人の描写がえらくうまいなと思っていたが、著者の「市役所の福祉事務所に勤務」という経歴を知って納得した。本書はその福祉事務所のケースワーカーを主人公にした連作集。
というとまず連想するのは「貧困と善意と正義と社会への怒り」の物語。どうにも面白くなさそうである。もちろんそういう要素もないことはないが、登場する「ケース」=社会的弱者からして一筋縄ではいかない面々だ。弱者ではあるが決して善意の弱者ではない。結婚詐欺や寸借詐欺をくり返したり、生活保護費をだましとろうとしたり、やくざな夫から助けてもまたやくざな男に惚れてしまったり、まあ本当に箸にも棒にもかからない底辺の「弱者」たちである。
助ける側のケースワーカーたちも決して理想的には描かれない。みなそれなりに仕事熱心ではあるが、章が変わって別のケースワーカーの視点に変わると、容赦なく批判されたりする。
こう書いてくるとどうも辛気くさい話しばかりそうだが、一話一話はちゃんと面白いから不思議だ。
日々働いて疲れたときに読むと元気がでるかもしれない(好みがありそうなので保証はしないが)。
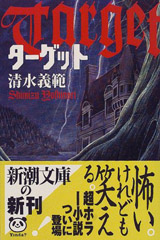 こちらは万人に好かれそうなすっきり面白い清水義範のホラー・パスティーシュ小説集。正直なところ清水義範はこのところ飽きてきていたのだが、本書はヒットでした。
こちらは万人に好かれそうなすっきり面白い清水義範のホラー・パスティーシュ小説集。正直なところ清水義範はこのところ飽きてきていたのだが、本書はヒットでした。
つまらなかったのは「乳白色の闇」くらい。「彼ら」も「オカルト娘」も典型的なホラーの構造をパロディにして笑わせる。「延溟寺の夜」はストレートなホラー。「メス」はサイコホラーというか日常にある恐怖の発見。ある意味いちばんこわい。
表題作は中編。クーンツの諸作や『リング』を連想させる本格ホラーだ。サスペンスフルな展開なのに最後がいかにも清水義範なのである。(悪い意味ではない)
 なぜ、突然リュパンが読みたくなったか、覚えていないが今さらながら読んでみました。ストーリー展開は面白く短編としてのキレのよさも十分だが、会話や人物造型はさすがに旧さが否めない。
なぜ、突然リュパンが読みたくなったか、覚えていないが今さらながら読んでみました。ストーリー展開は面白く短編としてのキレのよさも十分だが、会話や人物造型はさすがに旧さが否めない。
リュパンのキャラクターは颯爽としていてかっこういい。いかにもなパリジャンだが、女性に弱すぎだろう。というかあまりにも惚れやす過ぎ。お前は寅さんかと突っ込みたくなってしまう。
 マスコミにも頻繁に登場する解剖学の第一人者が案内する、口から肛門までの人体の旅。
マスコミにも頻繁に登場する解剖学の第一人者が案内する、口から肛門までの人体の旅。
人が人体をちゃんと見るというのはどういうことなのか、著者らしい皮肉が利いて、ちょっぴりユーモラスな文体で、思想や文明にまで筆はいたり、単なる臓器説明には終わっていない。
しかし、やはり面白いのは、人体各部分の、目からうろこが落ちまくる意外な知識そのものである。自分が自分のからだについて、いかになにも知らないのかということを思い知らされた。たとえば、しょっぱなからこんな疑問が呈される。
唇とはなにか。そんなことはわかりきっている。口のまわりの、あの赤いところ。
そうはいかない。解剖学では、あれを唇とは言わない。
鼻から下、両脇のしわの内側全体が「唇」として解剖学では定義されているのだが、それにはそれ相応の理由があることが、本書を読むとよくわかる。余談だが、絵を描く人が解剖学を勉強するといいというのはこういう知識を得るためだろう。赤い唇のような「記号」にとらわれず、人の顔の構造が明確にわかったような気になる。
では「赤い唇」とはなにかというと、これは消化管の粘膜に続く上皮が、顔の表面に露出してきただけ
なのだそうだ。他の動物は、口の中のものは口の中にちゃんとしまってある
のだ。
最後の肛門の章まで、悠揚迫らざる筆の調子は落ちないが、残念なのは、著者もあとがきで書いているとおり、消化管で終わってしまっていること。この調子でからだ全体について語り尽くしてもらいたかったものだ。

父親がドライブインシアターを始めるとこになり、テキサスの田舎町に引っ越してきた少年。森で焼け落ちた屋敷跡を見つけた同じ夜に少女の首無し死体が発見される。人生で最高に輝いていた夏休みと、それを彩ったおぞましくも懐かしい事件の顛末。
あの『ボトムズ』を上回る著者の最高傑作ということだが、小説としてのスケールの大きさでは、『ボトムズ』にはとても及ばない。ただ、それは『ボトムズ』と比べるからであって、本書が少年小説の傑作であることは間違いない。そう、少年小説である。ミステリとしてのしっかりした骨格を持ちながら、この小説の魅力はミステリ以外の部分にある。
ランズディールの小説に登場する人物はいつも魅力的なのだが、本書でも一徹な父親、気はいいが料理が下手な(そしてそれを気にしている)母親、美しくて「発展的な」姉、性的なことにまったく無知な「私」、彼のそばにいつもくっついている愛犬。いずれもいい味を出している。
そしてやはり『ボトムズ』と同じく、貧しい黒人たちのキャラクターがとてもいい。内縁の夫の暴力に虐待されている女中。意外とちゃっかりしていて、料理の腕は抜群だ。先代の経営者のときからドライブインシアターで働いているアル中の老映写技師。意外なインテリで、彼と主人公の少年との交流が本書の読みどころだ。
少年の夏休みが最高に輝いていた
のは、殺人事件に遭遇したからでも、性の知識を得たからでもなく、この老黒人から人生にかかわる多くの言葉をもらった日々だったからだ。そのことが、全てを読み終ったときに判然とする。やはりランズディールであるね。
「まあ、キットったら!」彼女の気分はたちまち変わり、顔にもいつもの茶目っけたっぷりの微笑がもどってきた。「まさか弱気になってるんじゃないでしょうね?わたしが手をひいてあげましょうか?」
「そうだなあ――ちょっと足がすくんでるみたいだ」彼は素直に認めた。「(略)さあて、ぼくのほうはもうもういつでもいいですよ(略)」
「QX,キット――はいってきて」
キットは侵入した。自分の中に息子が押しよせる最初のうねりのすさまじさに、彼女は思わず息をのみ、全身の筋肉をこわばらせ、いまにも苦痛の叫びをあげそうになった。彼女の手が本物の痙攣を起こし、それを握っているキットの指にかなりの力がかかった。どんな衝撃が来るのか彼女はわかっているつもりだったが、現実は違っていた――おそろしく違っていた。(略)彼女の存在の深奥にあるもっとも柔らかい敏感な中枢に突き立てられているような感じだった。
キットはその深みにぐんぐん突き入りながら(略)彼女の(略)を大きく押しひろげ、彼女自身そんなことができるとは思い及ばなかったほどすべてをさらけ出したのだ。(略)
彼女はふらふらの状態で身を起こし、顔をぬぐった。(略)刺激的な香りのする赤い液体をすすっているうちに、彼女の顔にも生気がもどってきた。「このところ何年も、何か足りないような気がしていたのも無理はないわ。ありがとう、キット。本当に感謝してる。あなたは……」
「それはもう言わないで」彼は母親に身をよせ、固く抱きしめた。彼女の顔が汗まみれで髪も乱れきっていることなど彼は気にもとめなかった
フランス書院文庫『熟母の寝室』読了。
…………嘘です。
引用元は宇宙冒険SFの古典『レンズの子供たち』の一節(「レンズマン」等の一部の語句を引用者が意図的に改変)。『第二段階レンズマン』に続くシリーズの最新刊は、いよいよクライマックス。ヒーローであるグレーレンズマン、キムボール・キニスンの五人の子供たち(息子と二組の双子の娘)が、父親をもはるかに凌ぐ超能力で、宇宙の悪の根源、エッドール人に最後の戦いを挑む。
キニスンの愛妻で、子供たちの美しい母親でもあるクラリッサは素質あるレンズマンでありながら、最終的な訓練を受けないでいた。その母親の能力を解放するために、超人となった長男キットが彼女を特訓するのが冒頭に引用したシーンだ。
精神エネルギーを制御する能力を得るためのイニシエーションではあるのだが、どうにも近親相姦を連想させる文章である。恣意的に「精神」とかそのたぐいの言葉を略してみただけで、官能小説の一場面のように読める(よね?)。
このシーンの前後にも親子の「おかーさんはなんて素敵なんだ」だの「これはあなたのためよ」だのという、こそばゆい科白が満載である。あきらかに作者は、超能力訓練というSF的場面を、母と息子の禁断の性愛を連想させるように狙って書いている。以前に一度読んではいるが、そのときは私も純真な高校生だったので、全然気がつかなかった。
かの謹厳実直、明朗快活、騎士道紳士道バリバリのドク・スミスがちゃっかりこんなことを書いていたとは。レンズマンについてそんなことを書いている解説やレビューにはお目にかかったことがない。いったい、これは新発見なのかという期待と、フランス書院文庫や富士見ロマン文庫に毒されたエロオヤジ(私だ)の単なる誤読なのかという不安で、いてもたってもいられなくなった(ちと大げさ)。
Googleでキーワード「レンズマン 近親相姦」を検索すると25件ほどヒットした。しかし、どれも古本屋のサイトなど、たまたま同一ページに単語が揃っていただけのページばかりだ。
なんだか、不純な私の妄想である可能性が高まってきた。
こういうときにはたよりになる、というかミもフタもないことも書込んでいるだろう2ちゃんの「レンズマンを語りたいんだよ 三惑星連合軍」スレをのぞいてみる。「近神相姦」なんていう言葉を見つけたが、残念ながらパロディ妄想ネタのようだ。
こうなったら、日本語以外のサイトをさがしてみるしかない。「incest Lensman」で検索するとえらくたくさんヒットする。ブックストアのページや「Lensman」というハンドルでエロっぽいネタを書いている人のページなどで、とても探すことができない。そこで「incest "Children of the Lens"」で検索し直すと、今度は4件だけヒットした。これがすべて、レンズマンに隠されている近親相姦テーマについて、言及しているページだった。やった!
のちのインセストテーマの後継者、ハインラインとのからみで書かれているのが多いので、ファンの方はじっくり読んで見ると面白いかもしれない。私は英語は苦手なのでさわりの部分だけでパス。
Interstellar Ramjet Scoop
↑12歳では気がつかなかったのも無理がないという私と同じような感想。
Sex Sells Science Fiction
↑昔からSFには性描写はあったんだぜ、ハインラインにもスミスにも。
Heinlein Reader's Discussion Group 06-10-2000
↑スミスは「7冊目のレンズマンは『レンズの子供たち』の近親相姦描写のため出版できなかった」と言っていた(ハインライン談)
Heinlein Reader's Discussion Group 10-12-2000 9:00
↑近親相姦テーマはレンズマンシリースが「神話」的世界に向かうということを示している(ハインライン談)。
キニスン一家はオリンポスの神々となるのか。元々レンズマンの善悪二種類の超越的宇宙人が争っているという世界設定は神話的ではあるけど。
ということで、残念ながら、私の新発見ではなかった(あたりまえだ)。
しかし、なぜ日本では見当たらないのだろう。旧きよきアメリカン宇宙SFという先入観が強すぎるのではないか。
新機軸のつもりか、解説の永瀬唯氏は、本書は反マッチョ思想としての先駆的なフェミニズムではないかなんて書いてるが、見当違いでしょう。そこまで深読みしていて、なぜインセストに気がつかないのだ。きっとフランス書院文庫を読んでいないからに違いない。それとも気がついていても言わぬが花、なのだろうか。
著者の断筆宣言解除後の最初の短編集である。
やはり断筆中に書いたという表題作がパワフルだ。「エンガッツィオ」とはつまり「えんがちょ」=スカトロテーマなのだが、あまりのえぐさに読後、妙にすかっとしてしまう。まさしくしつこい便秘がすっきり解消したようなさわやかさ?だ。
美貌だが異常に言葉が汚い女性タレントの話の「乖離」も面白い。ヒロインが放つリズミカルな悪口雑言がすさまじく、実に爽快である。
『族長の秋』を連想させる「首長ティンブクの尊厳」は、あきらかに北朝鮮の独裁者をモデルにしているが、5年も前の作品だ。
他にドラッグまみれの作家の悲喜劇「猫が来るものか」など、さすがの全10編。
シューペル=カンヌ──カンヌ近郊、ビジネスエリートの集うハイパー都市エデン=オランピアで医師による銃乱射大量殺人事件が起こった。深く、緩やかに育つ狂気を糧として―。銃声が静寂を破り、ビジネス・エリートたちの超楽園に闇が、ゆっくりと、口を開く―。人類の未来を占うサスペンス。
『コカインナイト』で架空の避暑地「エストレージャ・デ・マル」を舞台にしたバラードが、本書で選んだ舞台は、スーパービジネスマンのためのワンダーランドだ。最高のオフィス、宏壮な邸宅、充実した医療施設、独自の警備システム。当然ここに住めるのはエリート中のエリート、高度競争社会の「勝ち組」たちだ。
『コカインナイト』の遊民たちと違い、こちらは、麻薬を打って疲労を回復させ嬉々として出勤していくような連中だ。仕事中毒の彼らには精神のバランスを保つための秘密があった……
エリートたちの生理・心理を冷静に分析するパラードの皮肉な視線は実にクールである。もちろん、現実のエリートたちが、みな本書の登場人物のような狂気に侵されるわけではなかろう。しかし、ある変数を外挿することで、すぐそこまで来ている未来の狂気を生々しく描き出す──やはりバラードは究極のSF作家だと思う。
といっても本書はSFのカテゴリーには入らない。意匠もストーリーもミステリ仕立てではある。しかし、読後感はミステリとはだいぶ違う。既存のジャンルに分類しようがない。これはもう「バラードロマン」とでも呼ぶしかない。
 『天才と分裂病の進化論』は「
『天才と分裂病の進化論』は「人類だけが類人猿から隔絶した大きく複雑な機能と高い能力の脳を持っている。……なぜなのか
」という疑問への、生化学や遺伝学の立場からの一つの解答だった。
しかし、その疑問そのものは正しいのだろうか?本当に人類は類人猿から隔絶した存在なのだろうか?
最近、チンパンジーがかなりの知能を持ち、言語や数字について高い理解力を示すという話しを良く聞く。
著者は日本(世界でも)有数の類人猿学者だ。チンパンジーの数を記すのに「何匹」「何頭」と書かずに必ず「何人」と書く。このへんが日本の「サル学」が世界でユニークな地位を築いている一因かもしれない。ヒトがサルの延長であるという考え方にキリスト教文化圏の人間ほど抵抗感がないのだろう。
最初の二章では、野生のチンパンジーを対象に、道具の使用や教育、自然状態での彼らの社会性が確認される。
第三章では認識の発達。ヒト・チンパンジー・ニホンザルの乳幼児を対象に、鏡映像や道具などに対しての認知の違いとその発達経過を比較する。もちろん、ニホンザル<チンパンジー<ヒトの順で発達のスピードは早く、到達限界も違う。しかしチンパンジーは中間とはいえ、ニホンザルよりずっとヒトに近いのだ。段階によってはチンパンジーの方がヒトより発達が早かったりもする。
次の章からが本書の白眉だ。「言葉をおぼえたチンパンジー」アイを対象に、あらゆる事象への彼女の認識能力を細かく検証していく。
アイの能力にも驚嘆するが、興味深いのはいかにチンパンジーが物事を認識しているかを理解する、実験の詳細だ。
たとえば「チンパンジーは数がわかるのか?」という問題がある。画面に表示した点の数に対応する特定の数字のキーボードを押すという単純な実験はアイはすぐできるようになる。では、アイの数の認識はパッと見て直感的に把握しているのか?一つずつ数えあげているのか?どう実験すればそれがわかるのか?物の数と特定の文字の結びつきはわかっていても、その大小関係はわかっているのか?順序は把握しているのか?……次々興味深い疑問がわいてくる。それらを解明したり推論したりする実験の詳細が実に面白い。チンパンジーの能力の実測はもちろんだが、われわれがいかに物事を認識しているかを考え直させられる。人工知能を設計するのと同じ思考内容なのではないかと思う。
それらの実験の基本となるのが、アイの使う図形文字キーボードだ。彼女の図形文字の認識は、アルファベットより漢字に近い認識の仕方をしているらしい。その立証の中で「日本人とドイツ人の漢字の認識の相違」などという話題も派生してくる。どうも人類には日本人やドイツ人やチンパン人がいるようだ。
読んでいるうちにだんだんチンパンジーとヒトの差異が不明確になってくる。というより、ヒトとチンパンジーに違いはもちろんあるが、その境界は断崖絶壁ではなく、一続きの坂であることが明確になってくる。陳腐な言い方だが、サルを知ることはヒトを知ることでもありそうだ。
 『砂の女』や『箱男』で有名な、早逝しなければ確実に大江健三郎よりノーベル賞に近いところにいた大作家。というより私には、『第四間氷期』や『人間そっくり』などの同時代では抜きんでて知的な作品を書いたSF作家、としての印象が強い。前衛的かつユーモラスな戯曲も好きで、ほとんどの著作を読んだつもりでいたが、本書『燃えつきた地図』は読み落としていた一冊。
『砂の女』や『箱男』で有名な、早逝しなければ確実に大江健三郎よりノーベル賞に近いところにいた大作家。というより私には、『第四間氷期』や『人間そっくり』などの同時代では抜きんでて知的な作品を書いたSF作家、としての印象が強い。前衛的かつユーモラスな戯曲も好きで、ほとんどの著作を読んだつもりでいたが、本書『燃えつきた地図』は読み落としていた一冊。
失踪した夫の捜索を依頼された探偵の探索行という、典型的なハードボイルドミステリの設定で物語は進むが、ミステリ的予定調和なストーリー展開は望めない。
追うものがいつか追われていて、探偵がいつか自らを見失う。不条理な展開だが、最後までだれることなく面白く読める。次々登場するへんてこりんな人物、彼らがかわす妙に論理的な会話、異常に緻密な風景描写、すべてがいかにも安部公房らしい。
ユーモラスなのだけど、どこかうそ寒い孤独感がただよっている。自己憐憫的な孤独感ではなく、個々が切り離されていることがクールに明確になってくる乾燥度の高い小説世界。いかにも安部公房らしい。
段々実在感がなくなって切り絵のようになっていく依頼者の人妻が、不思議にエロティックだ。

 著者は『ジュラシック・パーク』の「琥珀に閉じ込められた蚊から恐竜のゲノムを抽出する」というアイデアを生みだした人だ。幅広いジャンルをカバーする科学者の作品らしく、本書は独創的な仮説が満載の破滅テーマSFだ。中心になるアイデアは「生態系のある重要な部分が欠落したらどんなドミノ現象が起きるだろうか」というもの。ペレグリーノが選んだ「重要な部分」は昆虫だった。
著者は『ジュラシック・パーク』の「琥珀に閉じ込められた蚊から恐竜のゲノムを抽出する」というアイデアを生みだした人だ。幅広いジャンルをカバーする科学者の作品らしく、本書は独創的な仮説が満載の破滅テーマSFだ。中心になるアイデアは「生態系のある重要な部分が欠落したらどんなドミノ現象が起きるだろうか」というもの。ペレグリーノが選んだ「重要な部分」は昆虫だった。
全編を通して、いかに昆虫が地球の生態系を支えているかが語られる。昆虫の占めていた生態学的地位に進出してくるのが肉食ダニ。雲のようなダニの大軍に次々と人間が殺戮され、居住不能地域が増えていく。
もちろん、破滅的現象は悪魔ダニだけでない。土壌のメンテナンスが不能となってほとんどの食用植物は絶滅する。ウイルス・バクテリアレベルにも異変が起こり、動物の体内でプリオン病原体が増殖していく。
なんと1998年刊行時に「プリオン=狂牛病」の流行を予言していたのだ。環境ホルモン汚染、O157やSARSなど新種の疫病が流行する現在、読んでいて正直背筋が寒くなるような内容である。このへん、科学的予言書としては実にすごい。
すごいが、小説としてはあまり面白くない。
同じ破滅テーマでも、バラードが『結晶世界』や『沈んだ世界』で書いた破滅しつつある世界の美しさなどはまったくない。もともと科学者である著者はそのようなものを書こうとは思っていなかったのだろう。
この後、小説世界では混乱する世相を逆手にとってアジテーターやテロリストが権力を奪取しようとする。対して一握りの科学者たちが現代のノアたらんと方舟建設に着手する。
……人間描写もハリウッド的な単純なものだ。
しかし実際に破滅がくるとすれば、バラードの描く形而上学的な格調高いものではなく、本書のような、ただただ悲惨な味も素っ気もないものであるような気がする。残念ながら。
 松本清張は戦後を代表する大作家であるだけでなく「大知性」であると思うのだが、今や二時間ドラマの(山村美砂や内田康男よりちょっとレべルの高い)原作者というイメージの方が強いような気がするのはちょっと淋しい。
松本清張は戦後を代表する大作家であるだけでなく「大知性」であると思うのだが、今や二時間ドラマの(山村美砂や内田康男よりちょっとレべルの高い)原作者というイメージの方が強いような気がするのはちょっと淋しい。
時代物にしてもミステリにしても戦後日本の頂点と言える傑作ぞろいだと思う。特に短編ミステリの切れ味(トリックがどうたらではもちろんない)は比肩するものがなかなかないほど素晴らしい。
著者は文春で三十年間清張を担当、現在は記念館の館長を務めている、誰よりも作家清張を知っている人だ。日本人の戦後史像を変えたと言っても過言ではないノンフィクションの大作『昭和史発掘』の取材秘話を中心に清張の実像を語る。
たぶん大部分の清張ファンは私も含め、清張自身の『半生の記』を読んで、清張は暗く貧しい青春時代を送った鬱屈した性格の持ち主と思っていることだろう。著者の回想と推理はこの清張観をいい意味でくつがえしてくれる。ちょっと清張の歴史推理を彷彿とさせるようだ。
すべての清張ファンは必読。
最近、海外ミステリー作家では個人的に一押しのランズディールの出世作(らしい)。ジャンルにまったくとらわれない著者らしい怪作。惹句によれば「伝説の奇想天外スラプスティック青春ホラーSF!
」。……う〜ん、まったくその通りというしかない。
テキサスのけちくさい田舎町のドライヴインシアターに週末を過ごしにやってきた若者たちが遭遇する怪現象。ドライヴインは異界と化し、閉じ込められた人々まで徐々に変貌していく……。
どんな怪現象なのか説明しようがないのだが、ドライブインで上映されているのが『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド ゾンビの誕生』『悪魔のいけにえ』『死霊のはらわた』などのバリバリのB級ホラーだというところから察してほしい。私は大好きだが万人にはお薦めしないタイプの小説(と映画)ではある。ナンセンスな不条理ホラーでありながら、友情や信念とか人間の尊厳とかを決して甘ったるくなく、ビタースィートな味わいで差し出してくれるのがこの著者の好ましいところだ。その語り口というのが、思い切りお下品な言葉つかいなのだから、こたえられない。
主人公が怪現象に遭遇したとき連想した映画が『マックイーンの絶対の危機/人喰いアメーバの恐怖』と並んで『美女と液体人間』だったのには嬉しくなってしまった。ランズディールの少年時代は、ドライヴインシアターでポップコーンを片手にB級SF映画ホラー映画を見るのが大好きだったのだろう。その無上の楽しみの中に東宝特撮映画が入っていたのは間違いない。

 著者は1972年にニューギニアで生物学者として鳥類の進化を研究していた。そのとき、一人の現地の青年とかわした対話が本書を書くきっかけとなったらしい。カリスマ的政治家でもあった青年は著者に素朴な質問をした。
著者は1972年にニューギニアで生物学者として鳥類の進化を研究していた。そのとき、一人の現地の青年とかわした対話が本書を書くきっかけとなったらしい。カリスマ的政治家でもあった青年は著者に素朴な質問をした。
「あなたがた白人は、たくさんのものを発達させてニューギニアに持ち込んだが、私たちニューギニア人には自分たちのものといえるものがほとんどない。それはなぜだろうか?」
最終氷河期が終わった時点では世界中どこも似たりよったりの採集生活をおくっていた。ところが1万3千年後にはスペイン人が南米大陸にやってきてインカ帝国を滅ぼした。なぜ、その逆ではなかったのか?直接的な要因はスペイン人が「銃・病原菌・鉄」を持っていてインカ人は持っていなかったからである。
現代社会ではヨーロッパと東アジアの民族及び北アメリカのヨーロッパからの移民の国が富と権力を支配している。アフリカ大陸や南米大陸の民族、オーストラリア大陸の先住民は白人の侵略者に土地を奪われ征服され絶滅させられ、現在も富や権力を手に入れるに至っていない。1万3千年の間に何が起ってこのような格差、不均衡が生まれてきたのだろう。
歴史家でも一般人でも単純に「支配した民族が優秀だったから」と考えがちだ。白人は優秀だから黒人を支配したのは(善悪は別にして)当然で、白人にはかなわないにしても支配されなかった分、日本人は黒人より(知的には)優秀、というのが大部分の日本人の口には出さない本音ではないだろうか。進化論的に考えても「適者生存」という言葉があてはまりそうな事例ではないか。
しかし、著者のダイアモンド博士はこのような見解を明確に否定する。
私は、ニューギニア人たちと行動をともにしはじめたときから、平均的に見て彼らの方が西洋人よりも知的であると感じていた。(中略)
歴史は、民族によって異なる経路をたどったが、それは居住環境の差異によるものであって、民族間の生物学的な差異によるものではない
ではこれほど大きな差異をもたらした居住環境の違いとはどのようなものだろうか?もちろん、たった一つの違い=原因ですべての結果がもたらされたわけではない。大陸の形状といった非常に大きな要因から動植物の分布まで多様な要因が複雑に連鎖しているのだが、著者は該博な知識とフィールドワークの経験を駆使して人類文明1万3年の歴史を解き明かしていく。
ちょっとしつこくなるほど検証は綿密で、歴史学・動物学・植物学・言語学と多分野にまたがっている。文章は平易でわかりやすいが、読み進んでいくと「人種」に対する先入観が壊され、新しい人類史観を否応もなくつきつけられる。なかなかスリリングである。本書を読んだあとに国際ニュースなどを読むと、だいぶ見えてくるものが違ってくるような気がする。壮大な人類史がつまった二冊である。
注釈が必要だと思うのが題名だ。白人のアドバンテージとして「銃」と「鉄」はわかるが「病原菌」とはなんだろう?むしろ、白人の入植者がマラリアで苦しんだり、梅毒が南米からもたらされた(とされている)エピソードから、病原菌は非征服者のアドバンテージではなかったのかと思う。
ところがマラリアや梅毒は例外的な事例らしい。白人の持ち込んだ病原菌で死んだ非征服者は、白人の銃や剣で命を落とした者よりはるかに多かったという。スペイン人がアステカ帝国を攻撃したときは、決して圧勝ではなかった。白人の方が武器は優れていたが、数においては先住民が圧倒していたからだ。ところが旧大陸からもたらされた天然痘がメキシコで大流行して、アステカ帝国の人口の半分以上が失われた。天然痘にかかりにくい免疫を持っていたスペイン軍は楽々と勝利することができたのだ。
ヨーロッパ人が疫病をもたらして先住民が死ぬ。この事実が意外と感じられることが、我々の人種的先入観の強さを物語っている。もちろん、なぜ、ユーラシア大陸の人間はそれ以外の大陸の人間にない大規模感染症の免疫を持っているのか、という謎も本書の中で解かれている。面白い。
 「ボーン・コレクター」というのは本編の連続猟奇殺人犯のことだ。このタイトルのつけ方は『ハサミ男』を連想させる。
「ボーン・コレクター」というのは本編の連続猟奇殺人犯のことだ。このタイトルのつけ方は『ハサミ男』を連想させる。
心ならずもボーン・コレクターを追うことになるアメリア・サックスは婦人警官。前職がファッションモデルという美貌の持ち主ながら、ナーバスでスピード狂。彼女とともに(というよりこちらが捜査の主人公なのだが)捜査をするのは元警察官で鑑識のスーパースペシャリスト、リンカーン・ライム。事故によって四肢麻痺となり、唯一動く薬指と口で操作するコックピットのようなベッドから(文字通り)一歩も動けぬまま、サックスを自分の手足目耳のように動かしてボーン・コレクターを追い詰めていく。この二人の関係は『羊たちの沈黙』のクラリスとレクターを連想させる。
捜査は主にサックスの破天荒な行動力とライムの超人的な頭脳によって行われるが、基本的にはチームプレイである。この辺はローレンス・サンダースの『魔性の殺人』を連想させる。しかし『魔性の殺人』は組織的捜査を緻密に描きながら、それを最後まで徹底できずに突然犯人が捜査側に特定されてしまうのだが、本書は徹頭徹尾、緻密で科学的な捜査をゆるがせにしない。
本書で描写される鑑識=犯罪捜査科学の知識量は半端ではない。検屍局長がヒロインという設定のコーンウェルのスカーペッタシリーズでさえ、本書に比べれば粗雑に思えてくるほどだ。だからといって無味乾燥な知識の羅列になるわけではない。ライムが明らかにした鑑識結果を元に、颯爽とサックスが行動するから、スリルにもサスペンスにも不足はない。
唯一不満なのは、やはり動機の稀薄さかな。きちんと説明されているようで、犯罪行為を産み出す必然性を納得させる描写が不足していることは否めない。ミステリーの犯人が「天から声を聞いて殺人を行う」タイプが主流になって以来の構造的欠陥だとは思う。動機以外の小説としての要素が良すぎるのでなおさら気になるのかもしれない。
そんな些細な欠点など全然帳消しにしてしまうのが、アメリア・サックスとリンカーン・ライムの心理のドラマだ。読後の印象が壊れるのが嫌なので、映画化されたビデオは見ないことにした。脳内の二人をそっとしておいてやりたいではないか。
 16の歳に弟子入りして以来76年、齢92歳にして、いまだ現役の挿絵画家の聞き書き伝。
16の歳に弟子入りして以来76年、齢92歳にして、いまだ現役の挿絵画家の聞き書き伝。
なにしろ画家・中一弥がプロになった頃は新撰組の生き残りがいて考証にチェックを入れていたという。師匠も月岡芳年の曽孫弟子位に当たるというのだから凄い時代だ。
中一弥が挿絵を描いた作家の代表は、やはり池波正太郎だろう。『剣客商売』や『鬼平』の挿絵と言えば絵柄が浮かぶ人もいるかもしれない。他にも挿絵を描いた小説家には、吉川英治から藤沢周平まで凄い面々が揃っている。
最近の若い作家の方が書く作品を読むと、むしろ、現代もの舞台の上で書いている印象を受ける。(中略)
時代考証はきちんとやっていますが、自分が書きたい部分は一生懸命にしらべているけど、あまり広くは知らない。江戸時代の文献をいっぱい読みあさって、その時代のすべてを自分のものにしているというタイプの作家は少ないように思います。(中略)
ただ、僕はそれでもいいと考えてます。今は、新撰組の生き残りが考証の間違いを指摘するという時代でもありませんし、むしろ、現代的な発想が、新しい時代小説を生みだしているのではないでしょうか。
飄々とした語り口が、挿絵職人として一筋に生きてきた人柄を感じさせて好ましい。趣味も古絵図と(モデルに着せる)着物の蒐集だというのだから、挿絵のための人生と言っていいだろう。なんともうらやましい人生である。
そしてもちろん、本書中に紹介されている数々の挿絵が素晴らしい。墨の濃淡だけで描かれた正確なデッサンと洒脱な構成は小さな縮尺でもみずみずしさを失っていない。最近のふんわりとした独自の画風を確立した絵もいいし、昔のかちっとした線の絵もあでやかでいい。
最後に本書の終章で著者が語る、90歳を越した画家の心境を引用しよう。頭が下がります。
僕も、写生ばかりを命じられて、そればかりをやっていました。ある時期から意図的に自分を壊そうと思って努力してきたけど、今でもリアルに偏っている。現実追求で一度鍛えあげてしまったものは、なかなか壊すことができないんです。例えば、床の間のある部屋で相対している二人の人物を描けといわれたら、僕は、資料を何も見なくても描くことができます。そこにいる人物を、写真に撮ったように描けるんです。(中略)
ただ、これではいけない。そこには夢というか、膨らんでいくイメージが欠如しているんです。人が僕の絵を褒めてくれても、自分の絵のことは自分がいちばんよく知っているから有頂天にはなりません。(中略)
僕の画風をどこまで壊すことができるかわからない。でも、夢や想像力の領域を広げる努力は、最後まであきらめたくはありません。
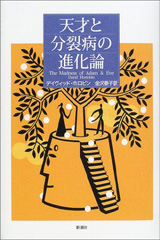 題名を見ただけで内容の予想をする人も多そうである。「天才を天才であらしめる遺伝子と分裂病の遺伝子は同じ、もしくは進化上非常に密接なつながりがある」というように。
題名を見ただけで内容の予想をする人も多そうである。「天才を天才であらしめる遺伝子と分裂病の遺伝子は同じ、もしくは進化上非常に密接なつながりがある」というように。
これは半分当たって半分はずれている。天才と分裂病が進化的に密接であることはその通りなのだが、本書で書かれているのは「天才と凡人の違いを生み出す原因」ではなく、「人類を人類であらしめている原因、それ以外(の類人猿)との差異を産み出す原因」なのである。
人間とその他の種の遺伝子構造は驚くほど似ている。(中略)チンパンジーや他の類人猿とは98から99%の遺伝子を共有している。
それなのに人類だけが類人猿から隔絶した大きく複雑な機能と高い能力の脳を持っている。なぜなのか。
いままでのマルクス的史観の進化論によれば、ヒトがヒトとして進化したのは、人類に加わっていた淘汰圧が原因とされていた。果実を採集するだけの密林での生活を捨て、草原に進出した人類が共同での狩などの複雑な労働を余儀なくされ、結果として脳が発達していった。
それは決して間違ってはいないだろうが、他の猿も決して楽園に住んでいたわけではない。
記述されている選択圧はどれも、人間や類人猿、霊長類に特有のものではない。(中略)環境因子だけでは、特定の目的に即した進化につながる遺伝子的反応をうみだすことはできない。環境因子にできることは、あらかじめ存在している突然変異、特定の環境に有利な遺伝子的反応を選択することである。(中略)
人間が独特であるのは環境因子が「独特」だったからではない。むしろそのような選択圧によって選択された遺伝子の突然変異が独特だったからに違いない。
ここで著者は人間の脳と類人猿の脳の物質的差異に注目する。人間の脳は類人猿より重く大きいが、それはいったい何が多いのだろう。それは「脂肪」である。脳だけではない、体中の皮下脂肪がヒトは猿より厚く豊富である。ヒトの脳に複雑な機能を与えているニューロンの構築にはリン脂質が欠かせない。そのリン脂質の正常な構築には幾種類もの脂肪酸が必須である。リノール酸とかドコサヘキサエン酸とか良く聞いたことのある「頭が良くなる」などど言われている物質たちも脂肪酸の仲間だ。
人類が輝かしき「万物の霊長」になったのは、実にこの「脂肪酸を効率よく取り込む」という小さな小さな突然変異が原因だった、というのが本書の主張だ。これなくしてはどんな環境の変化があっても人類はいまだ草原を徘徊する「裸の猿」のままだったかもしれない。とっくに絶滅していたかもしれない。
人類が進化し、狩猟・牧畜・農業と自分たちの環境を改変していくに従って、当然食生活も変化していく。著者は農業の発展により穀物が人類の食事の大きな部分を占めるようになったことで、摂取する脂肪酸のバランスが崩れやすくなったことを指摘する。この脂質のアンバランスが分裂病や躁鬱病といった人類特有の病の原因だというのだ。人類という霊長類の「天才」を発生させたのも、人類を「分裂病」にするのも同じ遺伝子の変異である。まさに「天才と気違いは紙一重」だ。
正直、私の読解力のせいなのか、論理が強引だな、飛躍してるな、と感じる部分も少なくない。しかしヒトの成り立ちを歴史的ダイナミズムから見ていく史観、進化観にならされてきた身には、ほんのちょっとの突然変異で偶然にヒトができた、というあっけらかんとした説はなかなか新鮮で魅力的ではある。
いくら脂肪がヒトを創ったといっても、皮下脂肪が多いほど人間的、ということにならないのは言うまでもない。
<前 | 日付順目次 | 書名索引 | 著者名索引 | 偏愛選書 | 次>